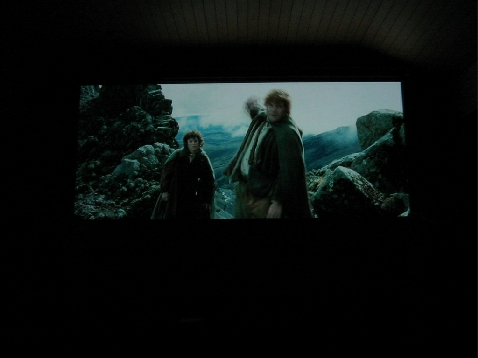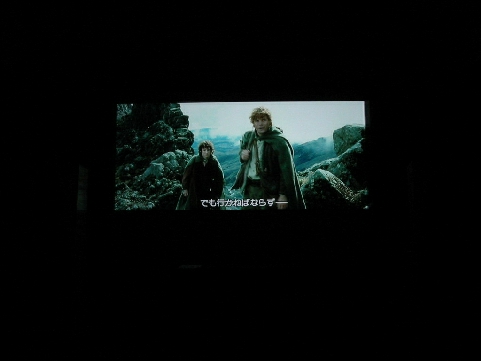6月-8月の雑記帳
○ 20040820 バランスケーブル
プリパワー間のバランスケーブルはこれまでレイオーディオのケーブルを使っていた。以前からフルカルダスを望んでいた。今回IK氏の義弟J君から放出品があり、念願のカルダスのバランスケーブルを導入することが出来た。
音はすばらしい。さらに実体感が向上、音楽が生き生きと鳴る。スケール感も出る。2メートルほど長いが仕方がない。現在PADのシステムエンハンサーにてバーンイン中。
○ 20040812 温度
室温が上昇するということで各コンポーネントの温度を測定することにした。
室温30度で、 (福島はこの3週間ずっと30度以上の日が連続している!!)
UX-1のトップカバー43度。トレイは45度以上。
デジタルハイビジョンチューナーは45度以上。
シナジー2i 42度
CA50-2 40度
モデル9Tのヒートシンクフィン上 42度
高周波を扱う機器は42度以上になっている。
室温+10〜14度の装置類が多い。
DPX1000の排気温度は計測していない。これが一番高そうだ。
なんと贅沢な趣味なのだろうということを痛感する。かたや、待機電力の削減でこまめにテレビの主電源を切っているが、片や、音質のために、トランスポート、プリアンプの電源は落とさない。
さすがにパワーアンプを通電状態にすると消費電力費用が月5000円以上高くなってしまうのでやめてしまったが、それでも贅沢には違いないね。
○ 20040705 スクリーン
シュチュワートのマリブを外した。
で、その隙間に、QRDを設置。
音像のにじみが激減。これはいい。SACD等の実体感がある音楽をきくとその効果は一聴瞭然。
フロントの吸音、反射は重要なことが改めて確認できた。アブフューザー、デフューザーの組み合わせで持っていける人は幸福だ。
そうでない人は持ち合わせの資材、機材でやってみるほか無い。
○ 20040628 ノイズフィルター
販売店Kさんから、AETの電源ケーブルには、フェライトコアのノイズフィルターが効くんですよ。といわれた。
以前、取り付かれたように、TDKのフェライトコアノイズフィルターを買い漁ったことがあった。
CDの音がまろやかになるとかで、CDのラインケーブルやら、ビデオの電源コードやら、いろいろなところに、フィルターをかました。
ところが、オーディオ・ビデオ機器に、このフェライトノイズフィルターを入れると、高周波のノイズを消す効果より、音や画に対するマイナス面の方が大きいことに気が付いた。ノイズを減らすより、必要な情報部分までカットしてしまうのだ。電源系から余計なものを省いていくと、ノイズフィルターの悪さが目立ってきたのだった。
最近は、外してあまったノイズフィルターを、家中の家電製品にかましてきた。扇風機、冷蔵庫、トイレの便座の電源、エアコン、炊飯器、常に通電している家電製品に次々このフェライトノイズフィルターをかましてきた。これらは効いた。直接オーディオ・ビデオ機器にかますより、こちらの方が効果あり。
そこへKさんからのアドバイス。
プロジェクターの電源に使っているAETの電源コードには、このフェライトコアのノイズフィルターがきくという。本当か?ピークが抑えられ、元気の無い画になりそうな予感がした。
とにかく、やってみることに。
うーん、なんとなくSNがよくなったような気がするくらい。劇的にコントラストがあがるわけではない。Kさんはコントラストが上がりよくなりますよ。といってはいた。
うちでは劇的な変化は無いものの、悪い方向へはいっていない。というくらいの変化だった。ということで、とりあえずつけておくことにした。
変化の度合いで言うなら、大きい順で
1.電源コンセント PSオーディオ製のコンセントにしたこと。
2.電源ケーブル AETのコードにしたこと。
3.専用に電源ブレーカーを設置し、プロジェクター専用線を引いたこと。
4.DVIケーブルを汎用品からクエストにしたこと
に次ぐ位の変化であった。
○ 20040614 プロジェクター台
プロジェクター台は、ご存知のとおり足場パイプなのだが、下地はそのまま金属地丸出しになっている。曲面だから直接反射する光は少ないと思われるが、無いに越したことはないので、ちょっと手を入れた。
パイプも叩けばカンカンと鳴るので、鳴き止めを考えていた。今回やってみたのは、水道管の断熱材。樹脂のパイプ状のもの。これを足場パイプに挿入してみようというもの。

上:パイプに断熱材固定用のアセテートテープを張り付けた。黒くなり反射は激減。これまでやるのだったら、DPX-1000の本体正面にも、反射防止用の対策を施したほうがいいかも。
下:パイプに挿入した白い断熱材。見事に鳴きが無くなった。縦・横・ななめ、主要な場所に挿入。鳴きがなくなった分画質が落ち着いたような気がする。(見た目は変わらないが、、、)コストは合計で1000円くらい。
○ 20040609 スクリーン
ワイド型で120インチ。でかい。画質はMALIBUがいいのはあたりまえだが、その差はわずか。画角の差を見てみる。同じ位置からの撮影で手ブレがあるのはご容赦ください。上がNAVIO120インチ、下がMALIB100インチ。実際の感じは、大きいほうが圧倒的に迫力がある。
ある場所を見ていると、違う個所を見るために、意識して目を動かさねばならない。画角が小さいときは目を動かさなくても画面を見ることが出来るが、大画面になると、あっち、こっちと目を動かさないと見えないようになる。
大画面になると気がつくこと。それは製作者の意図だ。顔のアップなど、どちらの眼に焦点が合っているのか。心の動きでピントが微妙に動くのだ。そのときの状況で、左右に二人いるときには、行動の中心のほうにさっと焦点が移動するのだ。これは大画面で特に実感できる。
以前UX-1導入時、ハイサンプリングで解像度が高くなって、俳優の「眼」の色で、心の中の状態(怒り、恐怖、愛情など)が良くわかるようになった、と書いた。今回大画面になったことで、それがさらに顕著になった。俳優は「眼」でも演技をしているのだ。
このような画面サイズ、画面位置の変更が容易に出来るのはDPX-1000のおかげ。3管式だったらこうはいかないし、ピント調整レジ調整などを考えるとやる気も起こらないことが、リモコンキー操作ひとつで容易に実行できる。
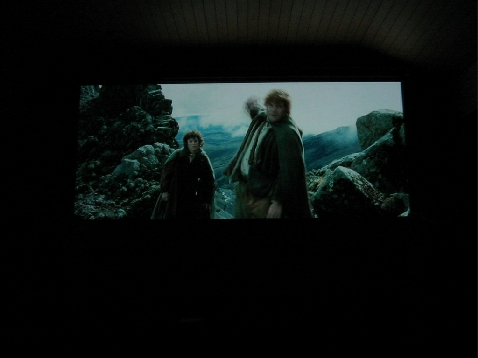
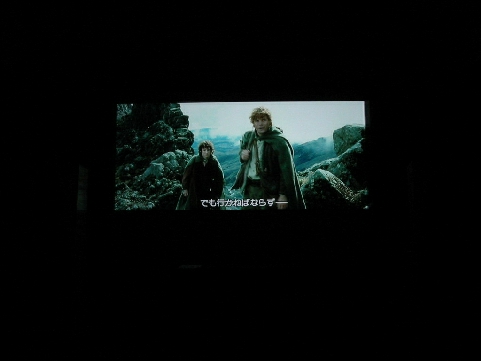
画質は、多少甘めなので、DPX-1000を再調整。多少シャープネスを上げ、色温度を変え、色濃度を濃くしてちょいちょい調整。で、かなりいける画になってきた。
色温度で画の印象がガラガラ変わってしまう。
○ 20040608 スクリーン
NAVIOのスクリーンが届いた。
長い。2780ミリある。これを、棚板アングルに取り付けぶら下げようという予定だ。
アングルは、鉄製、鉄心材入り外側木製、集合材木製があった。スクリーン取り付け基部を取り付ける関係で、集合材木製を準備。
アングルを壁に取り付け、スクリーンを取り付ければ出来上がりのはずだった。
予想しなかったことが起きた。アングルは集合材木製。これがばらつきがあった。L字型のアングルの直角が出ていなかったのだ。L字アングルの下端をそろえて設置したところ、スクリーンのアングルが直線にならない。L字アングルの直角が出ていない為、スクリーン取り付けアングルが波打ってしまった。 それで、アナログで調整。多少のゆがみはかまわない。

天井に近い方がNAVIOのスクリーン。左右から350ミリの位置に取り付け。

L字アングルにスクリーン取り付け基部をねじ止め。そこへスクリーンアングルをぱちんと取り付けで完成。本体が軽いのでこの方法が実現できた。NAVIOのスクリーンはごらんのとおり、スクリーンカバーがない。その分コストを落としているわけだが、合理的だし、実用上はまったく問題ない。そればかりか、カバーが無いので、共振する部分が無い、というメリットにもなっている。

L字アングルを壁の溝にそろえて取り付けたが、スクリーンのアングル面が波打つくらいばらつきがあった。
壁面から15センチ前に設置。壁がわにQRDのアブフューザーを設置する予定の為。
アンプの熱気の上昇気流で結構スクリーン自体がゆれてしまう。
○ 20040607 リアスピーカー
先日とあることから現用のLS1000が旅立つことになり、入れ替え作業を行った。
LS1000時リア音場の高さが出にくいので、四苦八苦して高さを稼いでいた。今回、以前使用していたSW、オンキョーのSL10と、B&WのCM1をセットでリアにセット。
CM1は底面の後ろ側が斜めにカットされているデザイン。カットされている部分で立たせると、バッフル面は斜めになる。音は空中へ放射されるような格好になる。スピーカー位置はLS1000よりさらに高くなった。
これは効いた。
DVDハンニバルCH3フィッシュマーケットのシーン。倉庫内で打ち合わせするときの天井付近でばたつく鳥の羽音。マーケット内での汽車がガードの上で「往来」する金属音。行ったり来たりする移動感がよく判るようになった。さらには銃撃音も多少もたつく感じがあるがバンバンと良く撃ち合っている。コンパクトスピーカーという点音源から発せられる音の効果として、リア音場の「高さ」が出るようになった。
ただし、パルシブな音の切れはいまいち。CM1では仕方がないか。