オーディオ雑記帳 2004年5月まで
○ 20040525 スクリーン
NAVIOというメーカーのスクリーンが安い。電動120インチ。ワイド型で実売5万数千円だ。これまでの常識だと電動スクリーンといえば20万円から40万円するのがあたりまえだった。それが一挙に10万以下!
販売店のご好意で、同社のスクリーンの貸し出し機を拝借することが出来た。 安かろう悪かろうではないか、という危惧があったのだ。
さて、先週水曜日に借りてきたのだが、この寸法が長いのだ。90インチのはずが、良く見ると100インチと書いてある。これでは一人での設置は無理だ。でも、今まで使っていたスプリングローラーのキクチスーパービーズ100インチよりずっと軽い。ようやく日曜日に、家族の手を借り設置成功。
画質。少し暗い。肌のつややかさが足りない。金属感がでない。と思っていたら、スクリーンが「グレイ」だった。「ホワイト」を所望していたのであるが、違うのだった。それでも、現用の「マリブ」に比較して、全然だめ、ということではない。
何よりも電動がかっこいい!ほとんど無音でスクリーンが上下する様は、なにか、すごくゴージャスなのだ。
というわけで、120インチのハイビジョンサイズの物を導入してみようと思う。
4:3 100インチ( 2032 × 1524 )でワイド画面を投射すると、投射サイズはワイド画面での90インチサイズ( 1992 × 1121 )くらいになる。面積比は、3096768:2233032=72%
100インチといっても4:3でのスクリーンサイズだと7割しか活用していないことになってしまう。
それを今回考えているのがワイドの120インチだ。
16:9 120インチは画面サイズ 2657 × 1494 = 3969558
現状4:3の100インチ画面に投影しているワイド画面、その面積2233032の1.8倍、約2倍の大きさになる予定。
これは、スーパービーズのスクリーン2つを重ねて実験した時と同じくらいの大きさ。会津坂下のIKシアターで実感していた、感動は画面の大きさに比例する、を実践してみたいと思うのである。

試し張りしたNAVIOのスクリーン。
○ 20040505 スクリーン
連休中、是非試してみたいことがあった。新プロジェクター台に設置した時、画面を巨大にしてもいけそうなことは確認した。今回販売店から80インチのスーパービーズのスクリーンを借りてきた。うちの元のスクリーンはキクチのスーパービーズ100インチだった。2つを重ねれば、倍くらいの大きさのスクリーンが出来るはず。
それを壁面いっぱいにしたらどうなるか、という実験をやった。
まずオリジナルを壁の左側最上部にあたるよう取り付け。次に借りてきた80インチのスクリーンを、かぶせるように吊り下げ。
ハイビジョンサイズで、130インチくらいの寸法だ。約4メートルかける約1.5メートル。
WOWWOWで、吹き替え版ハリーポッター秘密の部屋HVをやっていたのでそれを映写。
画面は見上げるような位置になるが、何よりサイズが4:3の100インチスクリーンに投射されるハイビジョンサイズの画面で約2倍!迫力はすごい。
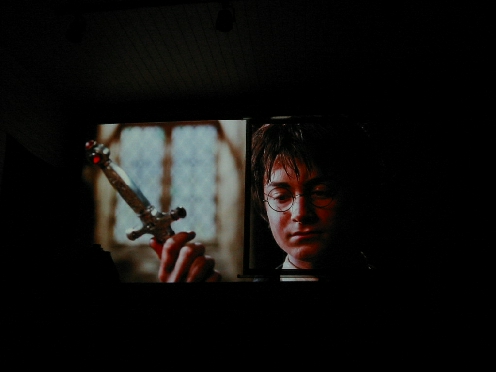
これじゃあ暗くて、よくわからないね。下の画面が同じ距離からとった普通の100インチのスクリーン。上の画面のポッターの顔の周囲にある黒枠は80インチスクリーンの枠。
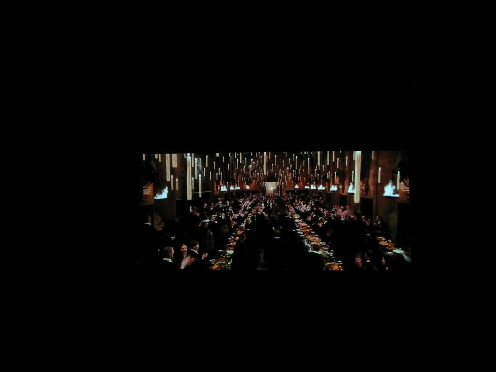
画面の俯角仰角が本当はあるんだけど画面主体で、撮っちゃったので、同じ高さに見えてしまっているが上のほうが高い位置にある。
結果。
画面位置が見上げる位置になるが、画面サイズの増大の迫力アップのほうが効果大。そしてDPX1000の能力としては、ハイビジョンサイズの130インチに拡大しても画力は落ちない。(4:3の150インチに投影しても大丈夫なのは会津のIKシアターで確認済み。)
もし130インチサイズのローコストスクリーンがあれば導入したいなあ。
今回は、DLPにスーパービーズのスクリーンという、販売店では勧めない組み合わせだったが、しゃきっとした表現は好感が持てた。また、リンギングはほとんど発生しなかった。画面上下の暗部が多少黒浮きするのが気になるくらいだった。DLPはスーパービーズでもいけるかも。
今回の実験は面白い結果をもたらした。これも、プロジェクターの位置が高いところにできたせいだ。天吊りにすると、もっとセッティングの自在度が上がるんだろうなあ。
○ 20040504 カセットデッキ
先日あるカセット好きの方とメールをやり取りする機会があった。ナカミチのデッキはいい!という結論だった。そこで、セッティングも一段落してきたので、ZX‐9を久しぶりにメインシステムに組み込んでみた。
今では録るものがなく、使わなくなってしまったカセットデッキだが、昔のテープを引っ張り出して、音質を確認してみることにした。
録音は1984年ころのマクセルXLⅡ。今回聴取したのはジェフベックのワイアードだ。当然自己録再もの。昔のテープには録音日時、録音機材、ドルビータイプなど几帳面に記載してある。まじめだったのだ。
ぱちっというスクラッチノイズがLPからの録音であることを表している。音はいい。ドルビーBを使っているが音がやせているということもない。これはすばらしい。
確認のためにこの数年前に入手したLPを再生してみた。当時の録音機材は過去のコンポーネントを参照していただくとして、今のLPの再生音と比べてみる。
うーむ、確かに高域の鮮鋭感はLPのほうがある。しかし、当時の録音機材の特徴だろうか、カセットは中低域がどっしりとしている。ロック的にはカセットのほうが面白いかも知れない。確かに、高域のハイハットのパシパシいう部分はLPのほうが確実にいい。ただ、20年前の録音がそれくらいの部分でしか違わないことに大きな驚きを感じたのだ。

買ったLPの音質が劣化していたのか、なんとも言えない。でも、ナカミチのカセットの音はこれだけ良かったのだと、現状のメインシステムに組み込んで改めて確認できたわけだ。ナカミチ恐るべし。
○ 20040501 スペーサー
シナジーのレッグは、ソルボセインのレッグが標準になっている。
それを替えてみた。TAOCのピンポイントシュー。
これはうまくなかった。
音が変に真横に圧縮されるようでいまいち。中域が強調される感じもいまいち。
で、元に戻した。
マルチ用アンプを、マルチアンプに替えて10日。
フロントとリアチャンネルのつながりがかなりよくなってきた。リアチャンネルがこれまでと同じものとは思えない、豪放な鳴り方になってきた。これで、スピーカーも変わったらかなりいい線になる予想だ。
ウイルソンのシステム6?120万円で中古の出物があった。ちと予算オーバー。出来れば、アバロンの出物があればうれしいな。
ソニーのTA‐P9000ESは売りに出すか。誰か欲しい人はいませんか?マルチチャンネルプリです。

○ 20040420 リヤチャンネルプリアンプ
先日ひょんな事から、チェロのアンコール1Mアニバーサーリーエディションが売りに出ていたので、試聴してみた。
シナジーを外して、チェロを入れてみる。
なんと自由闊達な表現なのだろう。ドン、シャーン!となる。ただその代わりボーカルがかなり大きくなってしまい、メインのフロントチャンネルに組み込むのには合わない。
そこでマルチのリヤチャンネルに使ってみる。いまは、ソニーのTA-P9000ESをマルチ用に導入しているが、フロントの2チャンネル再生時の表現とのギャップに、最近違和感を覚えていたのだ。リア用パワーアンプもたまたま試聴していたナカミチPA70CE。
DVDハンニバルCH3.音場感が一気に向上。こもりがちであった銃撃戦、爆発音も豪快に鳴る。これはいい。
これほど、プリアンプの力が再生音に影響があるとは。
もう一度、TA-P9000ESに戻してみるが、極普通の再生音。面白みは少ない。
そこで、センターチャンネルも、ナカミチのプリアンプをモノ使用とした。これで3ボリュームマルチチャンネルに挑戦。
これはいい。
実はチェロのフロント組み込みの試聴の際、ナカミチのプリアンプも、フロントに組み込んでみたのだ。中高域が張り出し、フレッシュな印象。だが、超高域、超低域の再現がいまいち。これではフロントには使えない。ところが、中域重視のセンターチャンネルでは、その傾向がうまく活き、また、ナカミチのプリパワーのセットでのうまみ?が功を奏し、センターチャンネルとしてまあまあの再現能力を持つ。パワーはPA70のブリッジ使用。モノアンプとして使用。
リヤは、UX‐1のリア出力から、アンコールへ。アンコールからPA‐70CEへ、となる。
この接続パターンでSACDマルチ再生。リンダロンシュタット、ホワッツニュー。ボーカルが天井から降り注いでくるような音場感。天使が空中に浮揚し、そこで歌っているようだ。
ピンクフロイド。狂気。これは1970年代に聴いていたものとは同一のはずだが、再生されている音は、すごい。時計のかちかち音が実にリアル。ボーンボーンという鐘の音がぞくぞくする。
サックスの音がセンターからこれでもかという生々しい音で鳴り響く。このディスクはすごいディスクなのだ。夜だったので、DVDマルチのディープパープル、マシンヘッドの再生は控えた。
TA-P9000ESのワンボリュームでの簡便さはいいが、それよりも、フロントチャンネルとの音質の整合性で、3ボリューム(マルチCHマルチアンプ)での再現性が勝った。
このチェロのプリは、電源コードでも音がガラガラ変わる。結構気むずかし屋さんだ。
○ 20040418 プロジェクター台セット
しばらく手がつけられなかったプロジェクター台作成。
日曜日にようやく時間が取れ、組み立てた。

○組み立てに4時間。水平、垂直をとるのが面倒。設計図は必要だ。プロジェクター台部は18ミリシナ合板二枚重ね。足場用パイプと、クランプで数千円のコスト。

○工事現場のようだ。一般の人は10数万出して、メーカー品の突っ張りポールを買ったほうがいいかも。右側上方は転倒防止の為の天井ツッパリ。大人がぶら下がってもがっちりしている。これをもう一個作って、室内トレーニング(懸垂)器具にするか?

○3点脚部。ここもピンポイント。地面打ち込み用のコ-ン型アタッチメントを使用。
結果。
頭の後方、背面がすっきりし、後頭部での音場感が向上。
後はパイプ鳴きの対策。砂を小袋に詰めてパイプ内に入れるか?表面をテープで巻くか?とりあえずは鳴いて気になってしょうがない、ということは無い。
画も現在台のエージング中なのでなんともなのだが、落ち着いてよい。
こうしてみると、DPX-1000の排気は高温だ。ジェフのアンプが高温だと思っていたが、主な室温上昇の犯人はDPX-1000だった。何とか、排気を冷ます方法は無いか。パイプで部屋の外へ強制排出する穴を壁にあけるか?何かいいアイディアないかな?ヤマハさん!!
排気を水冷化する。温水は風呂などに活用。
冬だったら、温風ヒーターの代わりにもあるが、それでも連続4時間を越えるとエアコン冷房の世話になるのだ。
昨日一昨日の室温は30度に達していた。死んでしまう。
○ 20040330 クライオ返答
前川電機から、クライオ処理について返答があった。
結論 クライオオーディオテクノロジー社の製品は、長期にわたって、クライオ処理の性質は変わらない。というもの。
クライオ処理製品を製造している、クライオオーディオテクノロジー社筒井浩氏からの回答。
世の中には、単に液体窒素につけるだけでクライオ処理と称する製品もあるのは確か。当社の製品は経験に裏付けられた製法により経年変化の無い製品を作り出すことに成功した。
極低温処理の温度、処理時間は、企業秘密なので公表できない。しかし、数年にわたる実地テストにより経年変化は無いことを確認している。
なお、温度によってクライオ処理の製品の分子配列が元に戻るのは、金属が溶融するほどの温度でなければ、変ることはないことを確認している。通常の使用状態では、クライオ処理の分子配列が、元に戻ることはない。
との回答を得た。データ-の開示が無い現在、その言葉を信じるしかない。
なお、現在のオヤヂのAVルームでは、音は熟成過程にあります。電源パーツのエージングには時間がかかることは以前書きました。電源ブレーカーの他にいろいろ要素が変わっているので、なんとも何ですが、進化していることには間違いないです。
○ 20040312
クライオ処理について、会津坂下のIKさんも、私も、経年変化について疑念があった。
電流の振動、電流が流れることで発熱する。それによって、クライオ処理された分子配列が元に戻ってしまうのではないか。確かに、電源パーツは常に50HZで振動している。発熱もあるだろう。その中で、通常品すなわちOFC等の選別品を使用しているわけではない、例のクライオ処理製品は、どのくらいの寿命を持っているのだろうか。
件の前川さんに質問のメールを出してみた。2003年3月はじめ。いまだ返信がない。ということは、クライオ処理は耐久性がないということの現われなのだろうか。
デジタルハイビジョン
先日DHX1のコンポーネントケーブル接続より、チューナーのD4接続のほうがいい、と書いたが、それならばと、D4端子から、コンポーネントケーブルに変換するオーディオテクニカの製品(3メートル)を使ってみた。
デジタルチューナーから、D4と、D4からコンポーネントケーブルの双方を比較試聴。
これは、D4 コンポーネントケーブル変換ケーブルの方が映像に力が出る。やはりケーブルの接触面積の差だろう。D4ケーブルは、接触面積が小さい。デジタルチューナーにコンポーネント端子があればよかったのだが、ないので、この変換ケーブルがベターな接続方式となった。
○ 20040308 緩み
先日発見した電源タップの端子部緩みは、確認の結果ほかは大丈夫だった。
良かった。火災など起きた日にはえらいことになる。
プロジェクター専用線設置に伴い、デジタル系のデッキ、デコーダー等の電源ををエアコン回線から取るようにした。
シナジー2iの電源コードを、SAラボのハイエンドホース純正にした。これまでは、オーディオかもんのシースをつけたハイエンドホースだったが、少し締まりすぎなので、変更。
シース付きハイエンドホースは、AACデコーダーに取り付け。
こうなってくると、5.1チャンネルプリの直出しパワーコードが気になってくる。どうしたものか。
○ 20040303 ブレーカーあれこれ
クライオ処理のブレーカーを取り付けた分電盤。もう一系統空きがあったので、そこからプロジェクター用の電源ラインを引くことにした。コンセントを検討。
販売店Kさんに相談したらPSオーディオを勧められた。ちと予算オーバーだったがそのコンセントを導入。
PSオーディオPOWERPORT(大元はHUBBEL社製のものをメッキ仕上げ等再加工したもの)


分電盤一番右がスーパークライオ処理のブレーカー。外観上は、まったく変わらない。
右から2番目が新設したブレーカー。(というよりスーパークライオブレーカーをつけて余ったものを活用)
2スケアのFケーブルと、3.5スケアのキャブタイヤケーブルがあったので、太い方のキャブタイヤで配線することにした。左が壁に直付けのコンセント。真似しないように。 (^^;
手前にきているのがプロジェクター用AETのケーブル。
さて、再生画像はどうなったか。
これまでは、エアコン専用線のコンセントから電源を取っていた。今回PSオーディオのコンセントに変えたのだが、その効果はすごいものがあった。
ロードオブザリング二つの塔。エクステンデッドバージョンチャプター14。死者の沼。
冒頭の岩のごつごつとした立体感。中央にフロド達が立つとき、日の光で、彼らのスモック(羽織っている布切れ)が光で透ける質感。遠方の沼の奥行き感。さらに奥の山の稜線の複雑さと、山の連なりの描写。
いずれも格段に向上。
白は白、黒は黒。はっきり出る。透明感も増した。フロドの肌のつややかさ、沼の水の透明感と、沈んでいる顔の描写。フロドが死者に引かれ、水に倒れこんだとき、奥からにゅっと飛び出てくる手の描写。思わず引いてしまうくらい立体的になった。
U571 CH25 敵機来襲。
皮ジャンの表面の描写。艦橋の裏側についている木材の質感。飛行機の翼の微妙な丸みの質感。いずれも向上。
結果大成功であった。ありがとうKさん。
ついでに、タップも改良。
○ タップ 今まではPADのCRYOL-2一ケ口だったものを、アクロテックの6N単線で結び、HUBBEL社のコンセントをパラ接続した。
気が付いたのが、端子部の緩み。タップのコードはオーディオクエストのヨリ線線材であったのだが、それが緩んでいた。より線は緩む、とは思っていたが、スカスカになっていたのには驚き。しっかり増し締め。他の自作部分でより線を使っているときは、注意が必要と痛感した。
この上に鉛インゴットを載せて使用。
○ 20040301 スーパークライオ処理のブレーカー
2月に石川シアターでデモがあった、スーパークライオ処理の電源パーツ群。そのうち電源ブレーカーを買ってきたことは、前に書いた。
月末をやっとこさ乗り切ったので、日曜の夜、電源ブレーカーの交換をやってみる気になった。
取り付けは、簡単。(工事は有資格者が行ってくださいと取り説に書いてある。そうではない場合は各自の責任の上でやること。)
先に購入してあったブレーカーはパワーアンプへの200Vのブレーカーと交換した。
なんと鮮烈な!
交換当初のインプレッションだ。中域がベールがはがされたように張り出す。強調されるのではなく、不純物が除かれたような聞こえ方。
石川シアターで聞いた、最低域へのレンジ拡大効果も多少あり。
しかしいかんせん、硬質感が強い。経験上、電源パーツは、エージングに2週間以上かかる。本製品もそうだろう。おそらくなじんでくるともっと音楽性が出てくるに違いない。
何曲か聴いていくうちに音楽の表情が出るようになった。
音場の広がりは抑制される方向。ただし、スピーカー間の音像の充実は目を見張るものがある。
大貫妙子CD アトラクシオン 一曲目の雷鳴の広がりは若干狭くなるものの、雷鳴、雨音の実体感は増加する。打楽器の響きも減るが、打撃音自体は、リアルになる。
綾戸ちえSACD ライフ 13曲目 よぞらのむこう。ボーカルの実体感が向上。
どうしても中域優先のおとになってしまう。これが合う人はどんぴしゃだろう。オヤヂのAVルームでは、エージング期待だ。それにしても、素性はいい物を持っている、ということは判る。これで、電源ケーブルもやったとしたら、中域が張り出しすぎて、聞くに堪えないことになったかもしれない。この辺も、石川シアターで感じた点と同じ。
スーパークライオ製品問い合わせ。
会津若松地区の代理店(福島県の北部にはここしかないようで、先日も前川さんは仙台まで取り付けに行ったそうだ。
前川電機商会
○ 20040225 デジタルチューナーとデジタルハイビジョンDVHS
デジタルチューナーのD4出力で今はハイビジョンを見ている。
ふと思い立って、DVHSのコンポーネント出力から、コンポーネントケーブルで見たほうが画質が良いのではないか、と思いついた。そこで、画質比較を行った。
D4ケーブルは、オーディオテクニカの普及品3メートル。コンポーネントケーブルは、オーディオクエストの銀メッキ線6メートル。
物量を見ても、コンポーネントケーブル接続のほうがよさそうだ。
早速、DVHS i-LINK チューナー出力 D4と、DVHSコンポーネント出力の画質をDVHS再生で比較視聴。
意外な結果。
なんと、デジタルチューナーのD4出力のほうが画像に切れがあり、よい。白ピークもきちんと出る。
それに対して、多少甘めのコンポーネントの画質。色の質感、奥行き感は若干良好だが、トータルの画質ではD4出力に負ける。
なぜだ?
販売店に訊いてみた。
ビクターのDHX‐1は、売価10万円を切る商品。その前の35000番は25万円の商品だ。当然コストダウンが図られている。どこら辺が安くなっているかというと、このコンポーネント出力回路なんだろうということ。なるほど。だから、物量投入のコンポーネントケーブルダイレクト接続より、i-LINK接続チューナー経由D4出力の方がきれいになってしまうのか。
ビクターさん、安いのは、だめ、なんて寂しいですね。
さらにDHX‐1の設定で、コンポーネント出力をD5に設定してみた。DPX1000では、相性が悪く、輪郭がぎざぎざっぽくなる。設定はD4のほうが良い画質であった。それでも、チューナー経由のD4接続のほうがいいのだから、この辺のデジタル技術については疑問が残る実験であった。
○ 20040214 石川シアター訪問
今日は会津坂下の石川シアターで、クライオ処理した電源によるデモがあるということで、視聴にいった。UX‐1も持ち込んで、ゴールドムンドのエイドス18MEVとの音の差も確認しようということになった。
まず、クライオ処理による電源コード(タップ)の音質比較。
作業はクライオ製品の代理店前川さん(有限会社前川電気商会)の有資格者が行った。
電源配電盤の一般のブレーカーを外し、クライオ処理のブレーカー(7500円)を取り付け。そこから、SCRV‐3.5(8スケア、3芯200V幹線用ケーブル)10メートルくらいの先に、汎用樹脂のコンセントボックスにクライオ処理のコンセント(SC‐2817ULP、明工社製のものを極低温処理をしたもの、3800円)を取り付けた電源ボックスを引いてくる。
これに、まずパワーアンプMODEL9TのDOMINUSを外し、タップに届くケーブルで接続。
音は、最低域の再生帯域が広がる感じ。JSバッハトッカータとフーガニ短調BWV565、アレシュバールタのオルガン演奏。最低音の音階が明確になる。
地響きに似た超低域再生だ。
元に戻してみると、低域が固まりになって力強いと一瞬感じさせるようになる。しかし最低音域の再生音が聞こえなくなってしまう。
次にトランスポートに先ほどのコンセントを使用。
中域の張り出しが出る。余分なものがなくなるからなのだろう。ダイレクトな表現になる。
低域の鳴り方は、パワーアンプの時と同じ印象。下が良く伸びる。
しかし、中域の張り出しは好き嫌いが別れそうだ。エイドス18の音場感を損なうような方向へ行ってしまう。
これは使えると、ブレーカーのみ購入した。
これを家のパワーアンプの元ブレーカーと交換すると、結構良い効果が出る予感がしたからだ。
○ シナジー2i 20040210
プリアンプを探していたところ、タイミングよく、出物のシナジー2iの情報が飛び込んできた。
渡に船!とばかりに即導入。
10日午後に到着したシナジー2iを開梱。氷のように冷たい筐体をしばらく室温に慣らすため放置。結露が怖い。夜になって接続をはじめる。
信号ケーブルのあと電源ケーブルを差し込んだが、何の反応もない。「これは不良か!?」
すぐさま取り説を読む。複数箇所に「この製品はマイクロプロセッサー搭載の為、誤作動するときがあります。そのときは電源ケーブルを抜いて30秒後に、再び接続して、、、」とある。とりあえず、電源コードを抜き差ししてみる。一部表示が出た。いいぞ。でも、本体のほうが反応がない。もう一度抜き差し。
やっとのことで、ボリューム表示と、本体のLED表示が点灯し、動作状態に入る。国内製品だったらきっとこんなことはないのだろう。海外製品のかわいいところである。
音は、かっちりとしてはいるが、まだ眠い感じ。システムエンハンサーをリピートにして翌日を楽しみにしよう。
○ 改造 AD‐100 20040208
ヤマハのAACデコーダーAD-100.音がいまいち品位がない。
特に薄いとか荒れているというわけではないのだがいまいち。
これは細い本機のパワーコードのせいもある。そこで、パワーコードを調べてみた。
1スケか1.25スケの細いコードが本体からでている。通常のコンポーネントとしてはかなりお寒い作りだ。サービスタップで、コンセントが一ケ口ついている。
そこで、フルカワのOFCパワーコード。2.0スケのもの。ナカミチの高級オーディオ機に標準で使用していたものだ。
これの別端にプラグを取り付け。サービスタップに取り付ければ、パワーコードを交換した効果がわかる。
OFCコードに変えると、そのままの場合より、音の輝きが増し、厚みも若干増える。いい方向に向くのが確認された。やはりこの製品もパワーコードで音が変わるのだ。
そこで、本格的に改造をはじめることにした。
方針は、サービスタップの開口部を利用して、3Pのアウトレットパーツを取り付ける。というもの。
本体のトップカバーを外して、内部を確認。パワーコードブッシングは、横にスライドすれば簡単に外れる構造。パワーコードはサービスタップ基板にコネクターで留められている。
これらを外し、サービスタップの開口部を、3Pアウトレット取り付けられるように穴を広げる。
幸い、鉄板がコンマ5ミリくらいの軟鉄でできている為、ニッパー等で作業ができる。
 音質確認用のパワーコード。これでパワーコードを替えると音がよくなることを確認。
音質確認用のパワーコード。これでパワーコードを替えると音がよくなることを確認。


金属カスを内部に残さないように細心の注意をして、取り付け出来上がり。
これで、通常グレードのパワーコードが取り付けられるようになった。音は、パワーコードの音が反映するようになる。


これでメーカー保証は受けられなくなった。もし、まねをして実行する人がいたら、それはあくまで自己責任のうえで行ってください。
○ 最終回不適応症 20040208
最近最終回が見られない。
スピルバーグのテイクン、再放送の時も録画に失敗。
サウスパーク。疲れて寝てしまい見逃し。
ナージャ ビデオ設定の日時が一日ずれていた為、見られず。
少し前は、毎回録画していたガンダムシード。これも最終回がなぜか失敗。
いったいどうなっているんだあ。最終回の内容が知りたいよお!!
○ ユニバーサルプレーヤー UX-1 20040123
待ちに待ったプレーヤーが到着。
冷え切った筐体をラックにセット。PADのシステムエンハンサーをリピートでセット。エイジングをはじめる。どのくらいでまともな音、画になるのかが不安。
音は、非常にまじめできっちりとした感じ。
画は、非常に落ち着いた感じ。
さあこれからどのくらい変わっていくか。
4日電源オンしっぱなし。リピート再生も繰り返し。夜中疲れ果ててみていて、コンポーネント出力とDVI出力の差があまりないじゃないか、など思ったこともある。それが4日目あたりからDVI出力720Pの画質が鮮鋭化してきた。
DVDミーシャ2002年ライブ冒頭の青が支配的なシーン。この青にノイズが乗らない。同じ色調の大画面表示などのシビアなソースもきちっと再現。この鮮鋭感は見事。ハイビジョン収録のDVD2003年ライブも非常に美しい再現。ハイビジョン収録ソースに相性がいいということか。
音は、2チャンネルのプリを導入前なので、ソニーのマルチプリのRCA出力を変換でXLRコードに接続している。
それでも、これまで聞こえなかった微小な情報がきちんと再生されている。
これはすばらしい。
早くまともなプリアンプを導入しなくては。
X01がSACDにおいてUX-1よりすぐれた再現性、というのもわかる気がするが未踏の空間。今はUX-1の能力をどれだけ引き出せるか、を考えよう。
今の所は、「すばらしい」という評価だ。

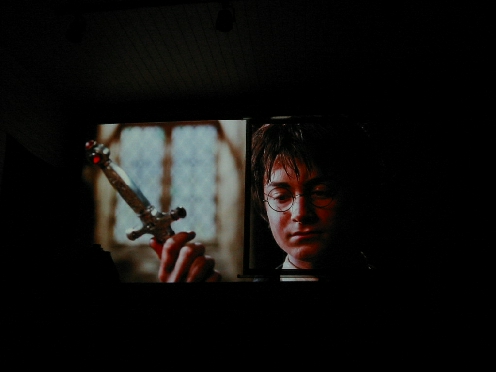
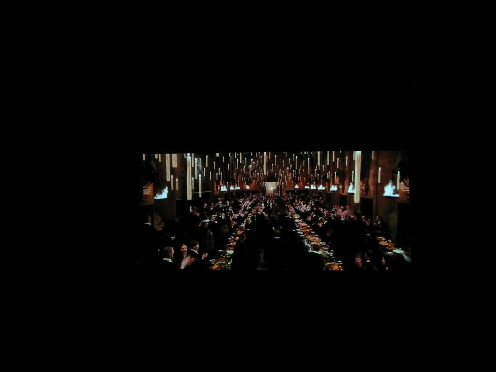








 音質確認用のパワーコード。これでパワーコードを替えると音がよくなることを確認。
音質確認用のパワーコード。これでパワーコードを替えると音がよくなることを確認。


