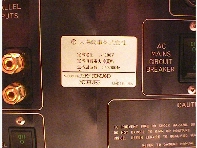ZAKKI 丂丂2005擭5寧偐傜12寧傑偱
仜丂20051231丂丂揹尮僐乕僪
丂1000俹偺揹尮僐乕僪傪拝扙幃偵夵憿丅乮夵憿偼丄堦斒偺恖偼寛偟偰恀帡傪偟側偄傛偆偵丅夵憿偟偨応崌偺愑擟偼偡傋偰帺屓愑擟偵側傝傑偡丅乯偄傠偄傠庢傝懼偊偰帋挳偟偰傒偨丅儀儖僨儞偺偼昳偑柍偔嵟弶偵扙棊丅僒僄僋偺偼僄乕僕儞僌傪婜偟偰巆偟偰傒偨偑丄偙傟偩偗側偺偐丄壒憸偑偵偠傓丅壒偵曄側僄僐乕惉暘偑忔偭偰偟傑偆偺偩丅偙傟偼巆擮丅傾僋儘僥僢僋偺俥働乕僽儖傪帋偟偰傒偨丅偙傟偼埲慜挳偄偨偲偒丄偁傑傝傁偭偲偟側偐偭偨偺偱丄慖戰巿偵擖偭偰偄側偐偭偨偑斕攧揦俲偺俲偝傫偵姪傔傜傟帋挳丅偦偆偟偨傜丄偙傟偑偼傑偭偨丅
丂1000俹偺傾僂僩儗僢僩働乕僽儖偐傜丄僲僀僘僼傿儖僞乕傑偱偺摫慄偵偼丄僫僇儈僠俹俙70偺撪晹攝慄梡偺儌儞僗僞乕働乕僽儖傪巊梡偟偨丅偟偨偑偭偰丄儌儞僗僞乕偺傕傝傕傝偟偨壒偑婎杮揑偵偮偄偰偔傞丅偙傟偵柍枴側傾僋儘僥僢僋偺働乕僽儖傪慻傒崌傢偣傞偲丄暼偺柍偝偑崌偭偰寢壥揑偵1000俹偺壒傪妝偟偄傕偺偵曄恎偝偣偨丅僟僀僫儈僢僋丄僔儍乕僾丄壒偺嬅廤姶丄壒応偺怺偝峀偝丄側偳柺敀偄曄壔偑偄偄曽岦偵岦偐偭偨丅偙傟偱僄乕僕儞僌偑恑傓偲傑偨柺敀偄偺偩傠偆丅
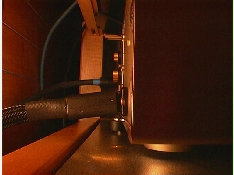 1000俹偺儕傾柺丂
1000俹偺儕傾柺丂
丂29擔偵俵俷俢俤俴9俿偑栠偭偰偒偨丅幒壏偵側偠傑偣丄嵞僙僢僥傿儞僌丅傗偼傝俵俷俢俤俴9俿偼傛偄側偁丅
丂偳側偨偐僫僇儈僠俹俙70俠俤丄俰俢俧俵俷俢俤俴2傪攦偄偨偄恖偄傑偣傫偐丠偳偪傜傕椙昳偱偡丅俵俷俢俤俴俀偼丄棤斨掤偺恖偑専摙偡傞偐傕偟傟傑偣傫丅
丂傑偨丄偨傑偨傑弌暔偩偭偨儌儞僗僞乕働乕僽儖俵儼2000偺僶儔儞僗2儊乕僩儖丄俼俠俙2儊乕僩儖丄45僙儞僠傕偺傪擖庤丅偦傟偧傟1000俹丄僔僫僕乕俀i娫丄僙儞僞乕梡俠俙5嘦偐傜僽儕僢僕傾僟僾僞傑偱丄倀倃亅1偺儕傾俼俠俙偐傜僔僫僕乕俀i傑偱偵憓擖丅
丂偙傟偑壒偑擹偄丅幙姶偼岦忋偡傞偑丄敀恖儃乕僇儕僗僩偑崟恖偵側偭偰偟傑偆傛偆側擹岤側枴傢偄偑弌偰偟傑偆丅崱傑偱偺傛傝偼幙姶偑椙偄偺偱偦偺傑傑摫擖丅壒偑屌傑傝偵側偭偰旘傫偱棃傞姶偠偑丄僕儍僘偑岲偒側恖偵偼傑傞働乕僽儖側偺偩傠偆丅
丂俀侽侽俇擭傕僆乕僨傿僆傪妝偟傫偱偄偒傑偡丅偱偼椙偄偍擭傪丅
仜丂俀侽侽俆侾俀侾侾丂丂僼僃傾
丂崱擔偼暉搰偺俶幮偺僆乕僨傿僆僼僃傾偩偭偨丅偦偺拞偱婥偵側偭偨傕偺偑庒姳偁偭偨丅
丂傾僐乕僗僥傿僢僋傾乕僣乮埲壓俙俙乯偺僽乕僗丅俙俙偺僗僺乕僇乕丄僩儔儞僗億乕僩丄傾儞僾傪暦偄偨丅僕僃僯僼傽乕僂僆乕儞僘偺僂僄儖傪柭傜偟偰偄偨丅偙傟偑丄傑偁傑偁椙偄丅嵞惗娐嫬偼僼僃傾夛応偩偗偁偭偰楎埆丅揹尮傕僿儘僿儘偺僥乕僽儖僞僢僾偱堷偒夞偟偰偄傞忬懺丅
丂儃乕僇儖懷堟偑枺椡揑偵僼僅乕僇僗偟偰偄偨丅
丂僜僫僗僼傽乕儀儖偺僗僺乕僇乕丅摨幮儈僯儅傛傝堦夞傝戝偒側僐儞僷僋僩僗僺乕僇乕傪暦偄偨丅偙傟傕丄拞堟偺僼僅乕僇僗偑崌偭偰偄偰慺揋側僗僺乕僇乕偩丅偨偩丄擻棪偑掅偄傜偟偔丄慻傒崌傢偣偺僾儕儊僀儞傾儞僾偱壒検傪忋偘傞偲丄拞壒検偱僋儕僢僾偟偰偄偨丅
丂價僋僞乕偺儕傾僾儘乮儕傾僾儘僕僃僋僞乕乯僴僀價僕儑儞儌僯僞乕丅價僋僞乕撈帺偺俢俬俴俙慺巕偵傛傞搳幩丅偙傟偼旤偟偐偭偨丅塼徎傛傝崟偑捑傓丅戝夋柺丅僾儔僘儅傛傝偪傜偮偒偼側偄丅墱峴偒偑弌傞丅側偳桪埵惈偼柧傜偐丅偨偩俇侽僀儞僠乮忋埵婡庬偼俈侽僀儞僠乯偲偄偆僒僀僘偑嵭偄偟偰偄傞丄偲塩嬈偝傫偼尵偭偰傑偟偨丅偦傫側偙偲偼側偄丅偙偺夋幙偩偭偨傜僾儔僘儅傛傝偄偄丅塼徎傛傝椙偄偟偱偐偄丅偙傟偼攧傟傞偱偟傚偆丄偲偄偭偨傜丄塩嬈偝傫偼擄偟偄婄傪偟偰傑偟偨丅幚攧俈侽枩偔傜偄偱僾儔僘儅傛傝椙偄偺偱偁傟偽丄摫擖偡傞恖偼憹偊傞偺偱偼側偄偐丅傑偟偰傗丄抧僨僕懳墳僠儏乕僫乕傕偮偄偰偄傞偺偩偐傜偙傟偼偍姪傔丅戞堦丄柧傞偄偲偙傠偱傕巊偊傞丄偲偄偆偺偑僼傽儈儕乕儐乕僗偵傄偭偨傝偩偲巚偆偺偩偑丅
仜丂俀侽侽俆侾俀侽俁丂丂戙懼婡
丂倀倃亅侾傪廋棟偵弌偟偨偺偱丄戙懼婡傪擖傟偨丅僫僇儈僠偺俢倁俢侾俆傪擖傟偰傒偨偑丄俢倁俢亅俼偑偐偐傝偵偔偄丅夋幙傕戝枴丅偲偄偆偙偲偱丄儂乕儉梡偺僷僀僆僯傾儘乕僐僗僩婡俢倁俆俉俆A傪帩偭偰偔傞丅塮憸俢俙俠侾俀Bit/108Mhz丄僾儘僌儗僢僔僽弌椡俼俧俛弌椡晅偒俽俙俠俢懳墳傾僫儘僌儅儖僠弌椡偲偄偆堦愄慜偩偭偨傜俀侽枩墌僋儔僗偺僗儁僢僋傪帩偭偨奿埨婡偩丅僫僇儈僠偲斾妑偡傞偲丄偡偭偒傝偟偨夋偑椙偄丅怓弮搙偑忋偑偭偰偄傞丅暥帤偺椫妔偺僗儉乕僘偝偑椙偄丅
丂倀倃亅侾偺傎偆偑墱峴偒丄慛塻姶丄棫懱姶偑桪傟偰偄傞丅乮偁偨傝傑偊偐丠乯壒偵偮偄偰偄偊偽倀倃亅侾偑埑搢揑偵椙偄丅乮偁偨傝傑偊偐乯強慒儘乕僐僗僩婡側偺偱壒偵偼婜懸偟側偄偱尒巒傔偨丅
丂僗僞乕僂僆乕僘俤俹嘨丅掅堟偺弌曽偑倀倃亅侾偲戝偄偵堎側傞丅乮偁偨傝傑偊偐乯偢偳乕傫偲棃傞偲偙傠偑柍偄丅夋偑寬摤偟偰偄傞偩偗庘偟偄巚偄偑偡傞丅
丂俢倁俢俆俉俆俙偺慻傒崌傢偣丄抲偒曽偲偟偰偼偁傝偊側偄丄嵞惗僔僗僥儉丄儔僢僋摍廃曈僙僢僥傿儞僌偱偼偁傞偑丄倀倃亅侾偑柍偄偺偱偼巇曽偑柍偄丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄偙偺俢倁俆俉俆俙偼倀倃亅侾偺侾侽侽暘偺侾壙奿偺妱偵偼丄壙奿嵎傪偳偆偺偙偆偺偲偄偆偙偲傪偁傑傝姶偠偝偣側偄弌棃偱偁傞偙偲偺傎偆偑嬃偒丅
丂僑乕儖僪儉儞僪偑偲偭偰偄傞曽朄傕側傞傎偳偲巚傢偞傞傪摼側偄丅僑乕儖僪儉儞僪偼僷僀僆僯傾偺儘乕僐僗僩婡傪峸擖丄拞恎偺儊僇晹丄堦晹塮憸張棟夞楬傪帺幮偺惢昳偵慻傒崬傫偱攧偭偰偄傞丅儕儌僐儞偼俹幮偦偺傑傑偩丅僑乕儖僪儉儞僪偄傢偔丄偙傟偩偗偺儊僇偼帺幮偱偼嶌傟側偄丄嶌偭偰傕僷僀僆僯傾傪挻偊傞偙偲偼偱偒側偄偐傜丄俹幮偺惢昳傪巊偭偰偄傞偺偩丄偲岞尵偟偰偄傞偺偩丅壙奿斾偼倀倃亅侾傪偼傞偐偵挻偊丄侾俆侽攞偐傜俀俇侽攞丄僑乕儖僪儉儞僪儕僼傽儗儞僗偵傕俹幮惢昳傪巊偭偰偄傞偲偡傟偽1000攞偵傕払偡傞丅偙偙傑偱棃傞偲丄壙奿斾傪榑偠傞偙偲帺懱堄枴偑側偔側傞丅
丂
丂俠俢偱丄僴乕僪儘僢僋傪攦偭偰偒偨丅僴乕僪儘僢僋傪挳偒偨偐偭偨偺偩丅偪傚偆偳僼僕僥儗價偺挬偺斣慻偱棃擔偟偨儃儞僕儑價傪僀儞僞價儏乕偟偰偄偨偺偱丄儃儞僕儑價偺怴晥僴僽傾僫僀僗僨僀丅偦傟偲斕攧揦偺捖楍扞偵僴乕僪儘僢僋偲偟偰攧偭偰偄偨偺偱丄僗僩儔僩僶儕僂僗乮僗僩儔僨傿僶儕僂僗偱偼側偄乯偺傾儖僶儉傪攦偭偰偒偨丅
丂側偤儃儞僕儑價傪攦偭偰偒偰偄側偐偭偨偺偐偼丄挳偄偰傒偰敾偭偨丅僴乕僪儘僢僋偲偄偆偵偼丄僴乕僪偠傖側偄丅娒娒丅偦偟偰儃乕僇儖偺惡幙偑偩傔側偺偩偭偨丅偁偺傛偆側偩傒惡偼岲偒偠傖側偄側丅
丂僗僩儔僩僶儕僂僗偼揟宆揑側僑僔僢僋僴乕僪儘僢僋傪栚巜偟偰丄偦傟偵敍傜傟偰偄傞媷孅側壒妝偩偭偨丅妋偐偵丄俢僷乕僾儖丄儗僀儞儃僂丄側偳偺捈宯垷棳偲偟偰偑傫偽偭偰偄傞偺偩偑丄儚儞僷僞乕儞偱偳偺嬋傕摨偠偵暦偙偊傞丅偙傟偩偭偨傜丄僐儞僠僃儖僩儉乕儞偱傕偍側偠偩側丅偱傕丄儃儞僕儑價傛傝偼椙偄偐両丠
仜丂20051128丂俬俲僔傾僞乕
丂夛捗嶁壓挰偺俬俲僔傾僞乕偵峴偭偰偒偨丅儅僀拰忋僩儔儞僗傪擖傟偨寢壥丄壒幙偑岦忋偟偨偲偄偆偺偱挳偒偵尵偭偨偺偩丅傑偨丄僙儞僞乕梡偵僐僸儗儞僗傪擖傟偨偲偄偆偺偱偦傟傕挳偒偵丄傑偨丄僷儚乕僐乕僪傪僟僀僫偐傜庁傝偨偲偄偆偺偱丄偦傟傕挳偒偵峴偭偨偺偩偭偨丅擔梛偼丄挰夛偱丄杊嵭孭楙傪幚巤偟偨偺偱丄偦偺廔椆屻偵夛捗偵岦偐偭偰弌敪偲偄偆帪娫懷偵側偭偰偟傑偭偨丅
丂摓拝偟偰壒傪暦偔丅妋偐偵掅堟偺妋屌偨傞幉偑旝摦偩偵偟側偄條偑偁傝偁傝偲暦偒庢傟偨丅偙傟偼惁偄丅
丂偟偐偟丄僷儚乕僐乕僪偺帋挳傕偺偼丄尰忬偺僾儔僘儅僪儈僫僗偵懳偟偰惁偔桪傟偰偄傞偲偄偆偙偲偵偼側傜側偐偭偨丅尰忬偺曽偑偄偄偺偱偁傞丅徻偟偔偼僟僀僫偺儊乕儖儅僈僕儞偵嵹傞偦偆側偺偱丄偦偪傜傪嶲徠偟偰偄偨偩偒偨偄丅
丂僩儔儞僗傪庢傝懼偊偨偽偐傝偺帪丄掅堟偑弌側偄忬懺偩偭偨丅崱夞偼丄僄乕僕儞僌偑恑傫偱偄偄忬懺偵側偭偰偒偰偄偨丅僄僀僪僗俁俉倁傕挷巕偑傛偔丄僠僃僢僋僨傿僗僋傪庢傝懼偊偰偼丄僷儚乕僐乕僪傪庢傝懼偊偰僠僃僢僋偱偒傞忬懺偵側偭偰偄偨丅
丂崱夞丄暉搰偐傜傕帇挳梡偵壗杮偐僷儚乕僐乕僪傪帩偭偰偄偭偨丅僑乕儖僪儉儞僪丄俹俽僆乕僨傿僆丄摿惢儀儖僨儞働乕僽儖丄摿惢僒僄僋働乕僽儖偩丅偙傟偵丄俬俲僔傾僞乕偺僾儔僘儅僪儈僫僗丄僟僀僫偐傜偺帇挳梡俹働乕僽儖丅俬俲僔傾僞乕偵偁傞偺偼丄僴僀僄儞僪惢昳丄偍傗偫偑帩偪崬傫偩偺偼儘乕僐僗僩惢昳丅乮偲偄偭偰傕僑乕儖僪儉儞僪偺傕偺偼僱僢僩偱5枩墌偔傜偄偺抣偑偮偄偰偄傞傜偟偄偺偩偑乯暉搰偐傜帩偪崬傫偩惢昳偼丄崱夞偺帋挳懳徾偱偼側偐偭偨偑丄傗偼傝僑乕儖僪儉儞僪偺働乕僽儖偼柺敀偄柭傝曽傪偟偨丅
丂僷儚乕僐乕僪偵傛偭偰丄壒偵僄僐乕惉暘偑偮偔丅偙傟偼夝柧偟傛偆側偑側偄榖偩偑丄帠幚側偺偩丅椙偄埆偄偱偼側偔丄壒妝偲偟偰妝偟傔傞偐偳偆偐偑僠僃僢僋億僀儞僩偵側傞丅
丂僟僀儗僋僩偵拞堟偑廩幚偟偰丄儊儕僴儕偑偮偔働乕僽儖傕偁傟偽丄幚懱姶丄寣偑捠偭偨昞尰丄岅傝偐偗傞儃乕僇儖偲偟偰暦偙偊傞働乕僽儖丅側偳側偳僠僃僢僋億僀儞僩偼悢乆丅偦偺側偐偱丄僾儔僘儅僪儈僫僗偼偄偄僷儚乕僐乕僪偱偁傞偙偲偼妋擣偱偒偨偺偩丅
仜丂20051031丂丂丂傾儞僾偲俴俹
丂俵俷俢俤俴8俽俹偺僙僢僥傿儞僌偼寢嬊僞僆僢僋偺儀乕僗傪奜偟偨丅崅堟偵偒偮偄僺乕僋偑忔偭偰偟傑偆偺偩丅偙傟偩偭偨傜丄捈抲偒偺曽偑傛偄丅俿俙俷俠儀乕僗傪奜偟偰丄弮惓僺儞億僀儞僩僼僢僩偺庴偗偵丄僆乕僨傿僆僥僋僯僇偺崌嬥儀乕僗傪憓擖丅偙偺崌嬥儀乕僗偼側偐側偐晭傟側偄慺惈傪帩偭偰偄傞丅偙偺崌嬥儀乕僗偺慜偵偼丄僗僥儞儗僗偺僺儞億僀儞僩庴偗儀乕僗傪巊偭偰傒偨丅偙傟偼僗僥儞儗僗偺壒偑偟偰偔傞偺偩丅僥僋僯僇偺崌嬥儀乕僗偼丄梋暘側壒偑偟側偄偺偱丄巊偄彑庤偑椙偄偺偩丅
丂偙傟偱丄俢倁俢僴儞僯僶儖俠俫俁偺憅屔撪偺旘傇偼偲偺塇壒偺崅偝偑弌傞傛偆偵側偭偨丅儅乕働僢僩偵擖傞偲偒偺壿暔楍幵偺捠夁壒偑丄屻曽偺忋偺傎偆偵掕埵偡傞傛偆偵側偭偨丅儅乕働僢僩廵寕僔乕儞偱丄儕傾偱懪偪崌偭偰偄傞敪朇壒偑嬤婑偭偰偒偨丅偦傟偱傕丄傑偩僶儞僶儞懪偪崌偆偡偝傑偠偝偑彮偟懌傝側偄丅僩儕僆俴俽1000偑儕傾俽俹偩偭偨崰偑側偮偐偟偄丅

僆乕僨傿僆僥僋僯僇丂俙俿682丂8儢擖傝丂丂掕壙3600墌

丂暉搰巗偺僴乕僪僆僼偲偄偆揦偱丄俴俹丄俴俢傕攧偭偰偄傞丅堦帪婜傛傝偼抣偑壓偑偭偰偒偨偺偱丄俴俹傪悢枃峸擖偟偨丅偦傟傪崱偺僙僢僥傿儞僌偱暦偄偰傒傞偲嬃偒偺楢懕偩偭偨丅
丂僞乕儞僥乕僽儖丄僼僅僲傾儞僾丄偼10擭埲忋摨偠丅僇乕僩儕僢僕偼怴偟偄偑丄偦傟埲忋偵僝僂僙僇僗偺儔僢僋丄僷儚乕傾儞僾偲偺愙懕働乕僽儖偺僌儗乕僪傾僢僾偑岠偄偰偄傞偺偩傠偆丅
丂傾儕僗1981擭偺夝嶶僐儞僒乕僩偺儔僀僽傾儖僶儉丅儔僀僽偩傠偆偲偄偆偙偲偱壒幙偼婜懸偟偰偄側偐偭偨丅偟偐偟丄偙傟偼岆傝偩偭偨丅娤媞懁偺憶壒丄扟懞偺俵俠丄傾儕僗偺妝嬋偑偆傑偔傑偲傔傜傟偰偍傝丄儈僉僒乕偺媄検偺崅偝偑擺摼偱偒傞偺偩偭偨丅
丂扟懞偺惡偺庒偝偵弌夛偊偨偩偗偱丄偙偺俴俹傪攦偊偨堄媊偑偁傞丅懠偵傕丄僕儍働僢僩偵偼僪乕儉偵側傞慜偺屻妝墍僗僞僕傾儉偺巔偑尒傜傟傞偟丄杧撪岶梇偺惡偼偁傑傝曄傢偭偰側偄偙偲傕傢偐傞丅傾儕僗偼偡偽傜偟偄儐僯僢僩偩偭偨傫偩側偁丄偲夵傔偰巚偄抦偭偨丅
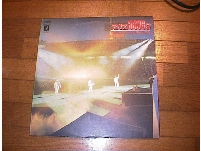
丂崅峑3擭偺帪偵媔拑揦偱暦偄偰偄偨巚偄擖傟怺偄彈惈儃乕僇儖傕偺丅儀僗僩斦偩偑丄巚偄擖傟偑偁傞偺偱攦偭偰傒偨丅僇乕儕乕僒僀儌儞偲丄儕僞僋乕儕僢僕丅僇乕儕乕僒僀儌儞偼偍傗偫偺僆乕僨傿僆帪戙偺慜偵挳偄偰偄偨傕偺丅摉帪挳偄偰偄偨儀乕僗偼俙俵儔僡僆偩丅偦偺屻丄俥俵仺僇僙僢僩偱暦偄偰偄偨偙偲傕偁傞偑丄俴俹偱偺嵞惗偼偙傟偑偼偠傔偰丅儕僞僋乕儕僢僕偼丄崅峑惗偺崰丄楒偲僐乕僸乕偺崄傝偵曪傑傟偨媔拑揦偱偐偐偭偰偄偨嬋丅偙傟傕丄偍傗偫偺僆乕僨傿僆慜巎帪戙偺傕偺丅俴俹偱偺嵞惗偼弶傔偰丅1979擭偐傜80擭偙傠偺儀僗僩斦偵側偭偰偄傞丅偳偪傜傕丄尰嵼偺嵞惗憰抲偱挳偔偲丄傛偄壒偱側偭偰偔傟偨丅巚偄弌偑徕彫壔偝傟傞傛偆側柭傝曽偱偼側偄丅媡偵朏弳側斵彈払偺儃乕僇儖偑偙傫側偵傕姶忣偑偙傕偭偰偄偨偺偐丄偲偄偆偙偲偑敾傝丄夵傔偰丄椙偄嬋偩側偁丄丄丄偲擺摼偡傞偺偱偟偨丅嵍塃椉僠儍儞僱儖偵怳傝暘偗傜傟偰偄傞奺妝婍丅偦偺僙僷儗乕僔儑儞偺椙偝傕俠俢暲傒丅偦傟偱偄偰丄僙儞僞乕偵尰傟傞儃乕僇儖偼丄旤偟偄側偁丅
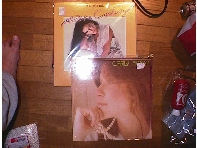
丂尰嵼偺僔僗僥儉偼丄僇乕僩儕僢僕丂俙僥僋僯僇俙俼俿2000丂僞乕儞僥乕僽儖丂儎儅僴丂俧俿2000倃丂僼僅僲傾儞僾丂僫僇儈僠丂俠俙50亅2丂偺俼俤俠俷倀俿丂擔棫揹慄俴俠俷俥俠俼俠俙働乕僽儖丂僾儕傾儞僾丂僔僫僕乕2i丂僇儖僟僗丂僿僢僋僗儕儞僋僑乕儖僨儞俆俠丂僷儚乕傾儞僾丂僕僃僼儘乕儔儞僪俢俧丂俵俷俢俤俴9俿丂丂俽俹働乕僽儖丂僇儖僟僗丂僿僢僋僗儕儞僋俧俆俠僩儔僀儚僀儎乕丂僗僺乕僇乕丂傾僶儘儞丂儗僀僨傿傾儞丂偲偄偆傕偺丅偙傟偵丄儔僢僋偼丄僞乕儞僥乕僽儖偑僋儚僪儔僗僷僀傾丄僼僅僲僀僐丄僾儕丄僷儚乕偑僝僂僙僇僗丅
丂偙偺傛偆側攝抲偱弶傔偰俴俹偺壒偺傛偝偑傢偐偭偰偒偨丄偦傫側忬懺偱偡偹丅儕僞僋乕儕僢僕偺俴俹傪暦偔偲丄壒偺椙偄俠俢偱枴傢偊傞壒憸掕埵丅僙儞僞乕嬻拞偵傎傢偭偲晜偐傃忋偑傞壧偄庤偺懱丅幚懱姶丅偙傟偑俴俹偱傕尰弌偡傞丅偙傟偼俴俹偱偼婜懸偟偰偄側偐偭偨掕埵姶偩丅俴俹偺曃怱丄僇乕僩儕僢僕偺僆乕僶乕僴儞僌丄側偳丄傾僫儘僌摿桳偺埵憡偢傟偱丄壒憸掕埵側偳偱偒側偄傕偺偩偲偽偐傝巚偭偰偄偨丅偦傟偑丄崱暦偔偲丄俠俢挘傝偺壒憸偑尰弌偡傞丅偦傟傕20悢擭慜偺儀僗僩斦偱偩丅偙傟偼偡偛偄丅偍偦傜偔丄悽偺僴僀僄儞僪偺奆條偼20悢擭埲忋慜偐傜丄偦偺儗儀儖偱丄昡榑摍傪偍彂偒偵側偭偰偄偨偺偩側丄偲巚偆偲丄崱傑偱丄寢峔僆乕僨傿僆偑岲偒偱俴俹傪暦偄偰偒偨偺偑丄幚偼丄俴俹偺幚椡偺悢暘偺1偟偐挳偄偰偄側偐偭偨偺偩偲抦傝丄彮偟偑偭偐傝丅偱傕丄偦偺摉帪庤偵擖傟傜傟傞丄暘憡墳偺僔僗僥儉偱妝偟傫偱偒偨偺偩偐傜巇曽偑側偄側偁丅
丂崱偙偆偟偰1980擭戙偺俴俹偼彮偟偯偮庤偵擖傟傞偙偲偼偱偒傞丅寢峔梸偟偄70擭戙偺傕偼偡偔側偄丅90擭戙偼壒妝帺懱巚偄擖傟偺偁傞傕偺偑彮側偔側偭偰偒偰偟傑偭偨偺偱丄梸偟偄俴俹傕彮側偄丅俴俹偐傜俠俢偵堏峴偟偰偄偔帪婜偩偐傜俴俹傕彮側偄丄偲偄偆帠忣傕偁傞丅
丂俴俢偼偐側傝尒傞婥偑偆偣偰偟傑偆儃働儃働姶偩偑丄俴俹偼傑偩傑偩挳偗傞儊僨傿傾偱偡丅乮俴俢傕幚偼壒偼偄偄傫偱偡傛丅偦傟偲彫偝栚偺夋柺偱丄棧傟偰傒傟偽俴俢傕傑偩尒傜傟傑偡丅乯
丂僗僥儗僆僒僂儞僪帍暿嶜丄儘僢僋偲僆乕僨傿僆偺嶨帍偑彂揦偵偁偭偨偺偱攦偭偰偒偨丅壒幙揑偵偼昡壙偑掅偄儘僢僋宯偺傾儖僶儉偵徟揰傪摉偰榑昡偟偰偄傞傕偺丅俴俹偺壒幙昡壙丄宆斣偼柍偄偑丄俠俢丄俽俙俠俢丄俢倁俢亅俙丄僶乕僕儑儞堘偄偺壒偺傛偟偁偟偑彂偄偰偁傝丄嫽枴傪偦偦傜傟傞丅摨偠傾儖僶儉柤偱傕丄偙傫側偵儊僨傿傾堘偄斉偑偁偭偨偺偐丄偲偄偆嬃偒丅帺暘偑帩偭偰偄傞斦偼偄偄壒僶乕僕儑儞偩偭偨丄偱埨怱丄丄丄側偳丅儘僢僋偑岲偒偱僆乕僨傿僆傕岲偒側恖偵偼堦墴偟偱偡丅
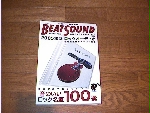
仜丂20051018丂偦偺屻
丂僐儞億偺棊偪拝偒偑弌偰偒偨傛偆偱丄壒傕偟偭偐傝偟偰偒偨丅
丂偙偺傛偆側揰偼僆乕僨傿僆偺妝偟傒側偺偩傠偆偹丅僄乕僕儞僌偼昁梫丄偲屘挿壀愭惗偼椡愢偟偰偄偨丅
丂崱夞偺僔僫僕乕偺2抜廳偹偼丄偦傟傪徹柧偟偰偄傞偟丄偁偣偭偰傗傝捈偟傪偡傞偲偄偆偙偲峫偊側偄偱條巕傪尒傛偆偲偄偆婥偵側傞傕偺丅婡婍偑儔僢僋偺怴偟偄娐嫬偵側偠傓偺偵偼丄悢擔偐傜悢儢寧偵媦傇偙偲傕偁傞丅乮晹壆偺応崌偼6儢寧埲忋偩偭偨丅乯崱夞偼丄怴偟偄僙僢僥傿儞僌偱丄側偠傓偺偵傕偆彮偟偐偐傞偐傕偟傟側偄偑丄埲慜偺僙僢僥傿儞僌偵嬤偄傕偺偑弌偰偒偰偍傝丄偄偄姶偠偵側偭偰偒偨丅
丂儕傾偺僷儚乕傾儞僾偺僙僢僥傿儞僌傕丄傕偆彮偟條巕傪尒偰懼偊傛偆丅
仜丂20051012丂丂柾條懼偊
丂MODEL9T偑栠偭偰偒偨偺偱丄僆乕僨傿僆偺妝偟傒傪嵞奐偟巒傔偨丅
丂MODEL8SP傪僙僢僩偡傞偨傔丄媣偟傇傝偵丄僐儞億傪堏摦丅偮偄偱偵愙揰傕杹偄偨丅応強偺娭學偱儕傾偺傾儞僾傪儕傾偵偼抲偗側偄偺偱丄慜偺傎偆偵偍偔偙偲偵偟偨丅僾儕傾儞僾偼僔僫僕乕2i偑2戜丄偙傟傪揹尮晹偲傾儞僾晹傪暿偵偟偰丄僟僽儖偵廳偹偰偡偭偒傝偝偣傞偺偲摨帪偵丄寢慄嫍棧傪抁偔偡傞偹傜偄丅
丂
丂儕傾梡MODEL8SP傪慜偵僙僢僩丅儀乕僗偼丄TAOC偺儀乕僗傪帋梡丅偙偺儀乕僗偼丄壒偑峝偔側傞孹岦偑偁傞偺偱丄偳偆偐丅傑偨偙偺幨恀偱偼丄擖傟偰偄側偄偑丄帋挳偺偁偲丄弮惓偺墌悕儀乕僗傪憓擖丅尰嵼僄乕僕儞僌拞丅
丂僔僫僕乕2i偺揹尮晹偼塃懁偵堏摦丅揹尮僐乕僪偑抁偄偺偱丄揹尮晹偼幬傔偵僙僢僩丅偙傟偱栚堦攖丅偐偭偙埆偄偑巇曽偑側偄丅
丂僾儕傪堦売強偵偡傞儊儕僢僩偼丄奺怣崋働乕僽儖偺棳傟偑摑堦偝傟丄偁傞掱搙奺僐儞億傑偱偺嫍棧偑嵟抁偵側偭偨丅
丂壒偼丄掅堟偑偢偭偲棊偪拝偔孹岦丅僙僢僥傿儞僌偟偨偽偐傝側偺偱丄偙傟偐傜棊偪拝偄偰偄偔偩傠偆丅
丂儕儌僐儞偱壒検挷惍偼偢偭偲偟傗偡偄丅偄偭偨傫儕傾偺壒検偺僎僀儞傪偁傢偣偰偟傑偊偽丄偁偲偼楢摦偡傞儃儕儏僂儉偱傜偔偪傫丅
丂
丂偙偺忬懺偱丄SACD儅儖僠丄DVD-A儅儖僠偺僨傿僗僋傪帋挳丅傟傟傟丠丠丠
丂僆乕偭偲丄PAD偺僔僗僥儉僄儞僴儞僒乕傪妡偗偰偄偨偺偱僙儞僞乕偺壒惡偑丄僼儘儞僩LR偺弌椡偵側偭偰偄偨丅
丂傫傫傫丠丠丠儕傾偺壒惡偑曄偩偧丅DVD僠僃僢僋僨傿僗僋偱丄僒儔僂儞僪壒惡傪妋擣丅傗偼傝儕傾偺嵍塃偑媡丅愙懕擖傟懼偊偱夵傔偰帋挳丅
丂
丂儕儞僟儘儞僔儏僞僢僩偺儂儚僢僣僯儏乕丅偆乕傫丄婥帩偪偄偄両偙偺儃乕僇儖偺柭傝曽偱僙儞僞乕偺愙懕儈僗偑敾柧丅
丂僇乕儁儞僞乕僘偺儕儅僗僞乕敾丅偆乕傫丄僇儗儞偑惗偒偰偄傞傛偆偩丅
丂僺儞僋僼儘僀僪偺嫸婥丅4嬋栚丅懪偪柭傜偝傟傞忇偑丄偄偄榗傪敽偭偰嵞惗偝傟傞丅偙偺忇偺柭傞応強偱丄儕傾偺嵍塃偺堘偄偑傢偐偭偨丅
丂偦偺屻丄DVD僒儔僂儞僪嵞惗丅乮塮憸晅偒乯
丂愙揰傪杹偄偨偣偄傕偁傞偑丄夋傕壒傕寢峔尦婥丅惗偒惗偒偲偟偨昞尰偱偄偄婥帩偪丅
丂偨偩丄儕傾偺壒惡偑偄傑偄偪丅
丂TAOC偺儀乕僗偵丄弮惓僗僷僀僋丄娫偵J1P偺惵偄僗儁乕僒乕傪夘偟偰偄傞偑丄僴儞僯僶儖偺CH3偺廵寕愴丅幩寕壒偑偄傑偄偪墦偄丅傕偭偲偽傝偽傝柭傜偟偨偄丅僄乕僕儞僌偱條巕尒丅
丂
丂

丂僔僫僕乕2抜廳偹丅揹尮晹偼僐乕僪挿偺娭學偱幬傔偵偟偐抲偗側偐偭偨丅傑偁偄偄偱偟傚偆丅
仜丂20051003丂僙僢僥傿儞僌
丂俵俷俢俤俴俋俿偑栠偭偰偒偨偺偱壒傪暦偗傞娐嫬偵傕偳偭偨丅媡僒僀僪偺僙僢僩傕僙僢僥傿儞僌傪傗傝捈偟偨丅
丂傑偢丄僗儁乕僒乕傪岎姺偡傞偨傔偵丄僝僂僙僇僗偐傜崀傠偡丅偁偄偐傢傜偢廳偄丅偡傞偲丄僝僂僙僇僗偺扞斅墶栘偺栚塀偟斅偑扙棊偟偰偄偨丅怗傞偲丄慜屻椉曽偲傕奜傟偰偟傑偭偨丅

丂恀拞偺崟偄庽帀斅偑奜傟偰偟傑偭偨偺偩丅儃儞僪偱愙拝丅壒揑偵偼柍偔偰傕傛偝偦偆偩偑丄傇傫側偘傞傢偗偵傕偄偐偢丄愙拝偲側偭偨丅庒姳偺庤捈偟傕偟偰丄嵞僙僢僥傿儞僌丅
丂儌僨儖9俿偼偦偺愄丄僝僂僙僇僗儔僢僋偑棃傞慜丄僗僷僀僋傪棜偐偣偰偄偨丅偦偺偨傔丄僗儁乕僒乕偼丄崟偄庽帀偺俰侾俹偺僗儁乕僒乕傪巊偭偰偄偨丅崱夞傂偭偔傝曉偟偰傒傞偲丄傗偼傝偦偺傑傑偩偭偨偺偱丄崱夞偼丄惵偄僞僀僾偵曄峏丅嵟嬤偺偼岤偝偑岤偄偺偱偐側傝儗僢僌偐傜偼傒弌偰偟傑偆丅幨恀偼丄俰侾俹偺惵偄僗儁乕僒乕傪庢傝晅偗偨忬懺丅
 僼儔僢僔儏偱旘傫偱傞偺偼偛垽沢丅
僼儔僢僔儏偱旘傫偱傞偺偼偛垽沢丅
丂壒偼丄偲偄偆偲僺儔儈僢僪僶儔儞僗偵側傝丄掅堟偺埨掕搙偼奿抜偵岦忋丅偮偄偱偵丄倀倃亅1偺儗僢僌偵偙傟傑偱偺俰侾俹偺峝偄崟偺僗儁乕僒乕傪憓擖偟偨丅崅堟偺朶傟偑柍偔側傝丄壒偺棫偪忋偑傝偑岦忋丅寢峔椙偄傛偆側偺偱僄僀僕儞僌偟偰傒傞偙偲偵偟偨丅
丂偦傟偵敽偭偰丄儕傾偺傾儞僾傕曄峏偟偨偄偺偩偑丄抲偔応強偺栤戣偱幚峴偵偄偨偭偰偄側偄丅
仜丂20050929丂俵俷俢俤俴9俿
丂俵俷俢俤俴俋俿偑廋棟偐傜栠偭偰偒偨丅
丂傗偭偲僆乕僨傿僆偵庢傝慻傓偙偲偑偱偒傞丅偙傟傑偱丄僫僇儈僠偺俹俙70俠俤丄俵俷俢俤俴8俽俹側偳傪擖傟偰偼傒偨偑丄俵俷俢俤俴9俿偺壒偲偺堘偄偵壒妝傪妝偟傓偙偲偑偱偒側偐偭偨丅
丂 丂嵞僙僢僥傿儞僌偺俵俷俢俤俴9俿丅
丂嵞僙僢僥傿儞僌偺俵俷俢俤俴9俿丅
丂傾儞僾儔僢僋偺僝僂僙僇僗傕丄幚偼庒姳庤捈偟丅僼儗乕儉偺傂傃妱傟偵懳偟丄嬥懏偺栘偹偠偱曗嫮偟偰偄偨偺傪丄栘偺偩傏偱丄曗嫮偡傞傛偆偵偟偨丅僼儗乕儉壓懁屻曽偺敀偔億僠偲尒偊傞偺偑偦傟丅
丂傑偨丄儗僢僌偺僗儁乕僒乕傪丄俰侾僾儘僕僃僋僩偺惵偄傕偺偵曄峏丅怴偟偄俰1俹偺僗儁乕僒乕偼偙傟傑偱偺傕偺傛傝1.5攞偔傜偄岤偝偑岤偔側偭偰偄傞丅幨恀偱傕惵偄僗儁乕僒乕偑妋擣偱偒傞丅偙傟傑偱偼丄俰1俹偺崟偄墌斦偩偭偨偑丄惵偄墌斦偵曄峏偟偨丅塃懁傕嬤擔庤捈偟偡傞梊掕丅
丂崱夞廋棟偡傞帪丄僋儗乕儉偵偟偰偄偨僩儔儞僗偺偆側傝傕寉尭偝傟偨丅偆側傝偼挷惍摍偱捈傞傕偺側偺偩傠偆偐丠

丂僙儞僞乕僗僺乕僇乕偺傾儞僾偲偟偰丄斾妑帋挳偟偨俹俙70丄俹俙70俠俤丄俵俷俢俤俴8俽俹丅
丂俵俷俢俤俴8俽俹偼丄壒偺僌儗乕僪偑堦婥偵岦忋偡傞偑丄惗惡偺傂偢傒丄偐偡傟丄擏擏偟偄(丠)昞尰偑庒姳屻戅偟偰傑偠傔側昞尰偵側傞丅俹俙70俠俤偼丄峝偄壒偩丅俹俙70俠俤偺僗働儖僩儞僔儍乕僔偼揝偱丄偑偭偟傝偟偨峔憿側偺偱丄偦傟偑壒偵尰傟偰偟傑偆丅擏惡偺惗惗偟偝偑尭戅偟偰偟傑偄丄柺敀傒偼彮側偄丅俹俙70丄俹俙70俠俤偲傕僽儕僢僕愙懕偱偺帋挳丅俵俷俢俤俴8俽俹偼俼俠俙擖椡偺曅僠儍儞巊梡偩丅
丂
丂寢嬊僙儞僞乕梡偵偼丄尰梡偺俹俙70偱峴偔偙偲偵偟偨丅偝偰丄俵俷俢俤俴8俽俹傪儕傾梡偵偡傞偨傔偵丄偳偙偵抲偙偆偐丅擸傫偱偟傑偆丅
仜丂20050902丂丂僗僀僢僠
丂僷儚乕僐乕僪傪奜偟偰揹尮僆儞僆僼偡傞傛偆偵偟偨偑丄僆儞偺帪丄偽偟偽偟偭偲儕儗乕壒偑偡傞偺偼惛恄塹惗忋偁傑傝椙偔側偄丅
丂僼儘儞僩偺僗僀僢僠偺傒偱偼丄揹婥傪怘偆偟丄擬偄偟偱丄揹尮偼愗傞偟偐側偄偺偱偡偹丅
丂偝偰嵟嬤帠柋揑側巇帠偱僾儘僕僃僋僞乕傪摫擖偟偨丅塼徎偱幨傟偽傛偄丄偲偄偆峫偊偱偁傞丅
丂1200儖乕儊儞丄僐儞僩儔僗僩俉侽侽丗侾偔傜偄偺傕偺丅EPSON偺埨攧傝昳偩丅10枩埲壓偲偄偆偙偲偱扵偟偨偺偱偁傞偑丄峫偊偰傒傟偽丄480俹偺僷僱儖偱俢倁俢嵞惗偵偼廫暘偲偄偆惢昳偩丅
丂幚嵺丄俢俹倃1000傪偦偙傊帩偪崬傫偱丄偲偄偆偵偼婋尟偡偓傞巇帠偩偭偨丅10暘偺1偺壙奿偱丄幨傟偽僆乕働乕偺姶妎偱摫擖丅偦偺寢壥偼丠師夞傊丅
仜丂20050818丂丂揹尮僗僀僢僠
丂儌僨儖俉俽俹偺庢傝愢傪撉傫偱偄偨傜丄儕傾僷僱儖偺僒乕僉僢僩僽儗乕僇乕偼揹尮僗僀僢僠偺戙傢傝偵巊偆側丄偲彂偄偰偁傝傑偟偨丅揹尮偺僆儞僆僼偼僼儘儞僩偺僗僀僢僠偱峴偄丄揹尮帺懱傪愗傝偨偄帪偼丄僷儚乕僐乕僪傪僐儞僙儞僩偐傜敳偗丄偲彂偄偰偁傞丅
丂偄傑傑偱丄揹尮傪愗傞偺偵丄僼儘儞僩丄儕傾偺僽儗乕僇乕偲丄愗偭偰偄傑偟偨丅偙傟偭偰傑偢偄偺偐側偁丠
丂崱屻偼丄揹尮僐乕僪傪奜偡傛偆偵偟傑偡丅
丂
丂僼儘儞僩偱帋梡拞偺儌僨儖8俽俹丅

丂僫僇儈僠偺1000俢俙俿偑挷巕偄傑偄偪偺偨傔丄僷僀僆僯傾偺俢俙俿俢07俙傪帋挳丅儊僇摦嶌偼戝忎晇丄奜憰傕傑偁傑偁偒傟偄丅
丂壒偼僷僀僆僯傾僒僂儞僪丅掅堟偑偳傛乕傫偲弌偰偔傞丅僨僕僞儖傾僂僩傪僫僇儈僠1000俹偵擖傟傞偲椙偔側傞偐丠
丂1995擭崰偺惢昳丅乮摉帪偺掕壙偼160000墌乯俫俽儌乕僪偱丄120暘僥乕僾偱60暘婰榐丅48俲偠傖側偔96俲婰榐傪峴偊傞偺偑攧傝偩偭偨丅偲偙傠偑丄傗偼傝壗傪榐壒偡傞偺偐丄榐壒偡傞僜乕僗偑柍偔偰丄偄傑偄偪帺屓徹柧傪棫偰傜傟側偐偭偨丅
仜丂20050810丂丂俵俷俢俤俴俉俽俹
丂曅僠儍儞偵擖傟偨儌僨儖8俽俹偼偝偡偑僕僃僼偺傾儞僾丅壒偑堘榓姶柍偔弌偰偔傟傞丅
丂儌僨儖8僔儕乕僘摿桳偺偝傜偝傜柭傞姶偠丅寉傗偐偵側傞姶偠偼丄儌僨儖8俢俠偲摨偠傛偆側柭傝曽偩丅
丂儌僨儖9俿偲偺戝偒側堘偄偼丄掅堟偺惂摦椡丅儌僨儖8SP偩偲儔僨傿傾儞偺掅堟傪惂摦偟偒傟側偄偱丄傎傢乕傫偲偟偨柭傝曽偵側傞丅偙傟傕傑偨丄挳偄偰偄偰柺敀偄偺偩偑丅憗偔丄儕傾偵擖傟偰丄僶儕僶儕柭傜偟偰傒偨偄丅
丂尰忬偼丄J1僾儘僕僃僋僩偺惵偄僗儁乕僒乕傪夘偟丄僝僂僙僇僗偺傾儞僾儔僢僋丅僷儚乕僐乕僪偼晅懏偺僐乕僪丅僴僢儀儖幮偺僾儔僌偑偮偄偰偄傞丅慄嵽偼儀儖僨儞幮偺傛偆偩丅SP抂巕偼弮惓偺曽傪巊梡丅慜僆乕僫乕偑摿庩側僆僀儖傪巊梡偟偰偄偨傜偟偔丄抂巕僇僔儊晹偺夞揮偑僌儕僗偭傐偄丅偄偭偨傫偼僼傿儕僢僾僗偺愻忩僗僾儗乕偱愻忩偟偨偺偩偑姰慡偵偼庢傟偰偄側偄傛偆偩丅
丂儕傾偵帩偭偰偄偔慜偵丄椉僠儍儞僱儖嬒摍偵巊偆傛偆偵丄嵍塃CH偺擖弌椡僐乕僪傪擖傟懼偊側偑傜巊偭偰偄偐偹偽丅
仜丂20050731丂丂俵俷俢俤俴俉俽俹
丂儕傾梡偵儌僨儖8俽俹傪摫擖偟偨丅僱僢僩偱攧傝偨偄恖偵傔偖傝崌偭偨忣曬傪夛捗斅壓偺俬俲偝傫偐傜忣曬傪傕傜偭偰丄悢夞儊乕儖偺傗傝庢傝傪偟偨忋偱丄岎徛惉棫丅崱夞傕椙偄曽偱傛偐偭偨偱偡丅
丂偦偺傛偆側忬懺側偺偱丄偲傝偁偊偢僼儘儞僩偺嵍懁偵擖傟偰丄曅僠儍儞偢偮僄僀僕儞僌傪偟偰偄偙偆偐偲巚埬拞丅


丂旤偟偄僼儘儞僩僷僱儖偵庒姳偺偡傝彎偑丅儕傾僷僱儖丅壓抜偺俽俹僞乕儈僫儖偑懠幮惢偵岎姺偝傟偰偄傞丅
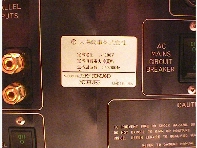
仜丂20050710丂丂僷儚乕僐乕僪
丂儕傾偺傾儞僾僕僃僼偺儌僨儖俀偺僷儚乕僐乕僪傪丄僇儖僟僗偺僑乕儖僨儞儕僼傽儗儞僗偵岎姺偟偨丅昗弨昳偼儀儖僨儞幮偺昗弨暔丅
丂憗偔懼偊偰偍偗偽傛偐偭偨丅
丂懼偊偨寢壥偼丄傛偄丅
丂壒偺幙姶偑岦忋丅崅偝傕弌傞傛偆偵側偭偨偺偑惁偄偲偙傠丅
丂俢倁俢僴儞僯僶儖俠俫丏俁偺朻摢丄偼偲偑偖偆偖偆丄偽偝偽偝偽偝偲丄寶暔偺拞傪旘傫偱偄偔偺偩偑丄偦偺崅偝丅儅乕働僢僩偵幵偑擖偭偰偄偔偲偒丄屻傠偺崅壦傪憱傞壿暔楍幵偺憶壒偺崅偝丅廵寕愴偺帪偺儕傾偱懪偪崌偆廵岥偺崅偝丅側偳夵慞偝傟偨丅
丂俽俙俠俢僺儞僋僼儘僀僪嫸婥4嬋栚丄帪寁偺忇偑偑乕傫偑乕傫偲懪偪柭傜偝傟傞丄偦偺懪寕壒偺儕傾儖偝丄僼儘儞僩儕傾偺偮側偑傝丄偦偟偰丄傗偼傝忇偺崅偝偑椙偔弌傞傛偆偵側偭偨丅
丂偙傟偐傜僄乕僕儞僌偑恑傫偱偳偺傛偆偵側傞偐丄妝偟傒丅

丂椙偔尒傞偲丄巊偭偨愓偑側偄丄怴昳偺傛偆偩丅僾儔僌偺僽儗乕僪偵嬥懏偑偙偡傟偨愓傕側偄偺偩丅
丂儕傾偺壒偑傛偔側偭偰偔傞偲丄僼儘儞僩偺壒偲側偠傫偱丄偮側偑傝偑傛偔側偭偰偔傞丅壒応偑宍惉偝傟傞偺偩丅
丂斕攧揦俲偝傫偱丄倄俙俵俙俫俙偺怴惢昳俙倁傾儞僾傪暦偄偨偑丄僙僷儗乕僔儑儞偑丄偡偛偔偰丄偄偐偵傕丄塃偑柭偭偰傑偡傛丄屻傠偺嵍偑柭偭偰傑偡傛丄偲偄偆壒偺嵸偒曽偩偭偨丅壒惡僨僐乕僪偺僨僶僀僗偑嵟怴僞僀僾偩偲偄偆丅僨儌偵偼岲搒崌偐傕偟傟側偄丅堏摦姶偑柧椖丅
丂偦傟偲偼傑偨堘偆傾僾儘乕僠側偺偩側偁丄偆偪偺僔僗僥儉偼丅
仜丂20050623丂丂兝

丂壠梡偺兝僨僢僉俫俥705偑偍偐偟偔側偭偨丅俼俤俠偡傞偲偒偼僇僂儞僞乕摦偔偺偩偑丄嵞惗偡傞偲丄僇僂儞僞乕摦偐偢丄夋傕壒傕弌側偄丅憗憲傝偡傞偲丄塮偭偰偄偄傞偺偑尒偊傞偑俹俴俙倄偵偡傞偲尒偊側偔側傞丅
丂偄傛偄傛壠偺儀乕僞偺嵟怴婡俽俴俀侾侽侽傪壠掚梡偵搳擖偡傞偙偲偵側偭偨丅巕嫙偼乽偐偭偙偄偄偹偊乿乽崱兝偺僨僢僉偭偰攧偭偰傞偺丠乿側偳慺杙側堄尒偑師乆偲丅嵟怴偲偄偭偰傕丄15擭傕偺側偺偩偑丅
丂偨偩僆儕僕僫儖偺儕儌僐儞傪弌偡偲丄巊偄偯傜偄偺堦尵丅僨僓僀儞偼枹棃揑乮僔傾僞乕儅僗僞乕偺儕儌僐儞偲摨偠僞僢僠僷僱儖曽幃丅僜僯乕傕堦帪婜偙偺儕儌僐儞傪僔儕乕僘偱弌偟偰偄偨偑丄巊偄偯傜偄偨傔偐丄巔傪徚偟偨丅乯

丂偙偺2100偼堦戜栚傪岎姺偟偨偑丄屻偼偍偍傓偹椙岲丅夋幙偼儀乕僞僴僀僼傽僀婡拞嵟崅丅僉儍僾僗僞儞儌乕僞乕偑摦偐側偔側傝丄嶐擭岎姺偟偨偑丄屻偼戝忎晇丅偁偲壗擭帩偮偩傠偆偐丠
仜丂20050617丂丂揹尮僐乕僪

丂20傾儞儁傾偺僐僱僋僞乕偑偮偄偨僇儖僟僗偺僑乕儖僨儞儕僼傽儗儞僗傪峸擖偟偨丅弶傔偰丄儎僼乕偺僆乕僋僔儑儞偱擖庤偟偨傕偺偩丅偙傟傑偱丄僆乕僨傿僆偺攧攦偱僩儔僽儖偼偁偭偨偙偲偑側偄丅屆偔偼丄僗僥儗僆帍丄俥俵儗僐僷儖帍丄俥俵俥俙俶帍側偳偱丄攧傝傑偡攦偄傑偡棑傪巊偭偨偙偲偑偁傞偑丄偡傋偰栤戣側偟偩偭偨丅崱偺怳傝崬傔嵓媆偺悽偺拞傪尒傞偲丄僆乕僨傿僆垽岲壠偺奆條偼椙幆偁傞曽偑懡偄偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐丅
丂偝偰丄偙傟偼儕傾偺僕僃僼偺僐僱僋僞乕梡偵崌偭偰偄傞偺偱丄偝偭偝偲岎姺偡傟偽傛偄偺偩偑丄側偐側偐偦偺婥偵側傟側偄丅
仜丂20050606丂丂俤俿俠
丂巇帠梡偺幵偵俤俿俠傪偮偗傑偟偨丅暉搰巗偐傜5000墌偺曗彆偑弌傞偐傜偱偡丅埲慜傕庢傝晅偗傛偆偲巚偭偨偙偲偑崌偭偨偺偱偡偑丄俤俿俠偺僇乕僪偑側偄偲丄僙僢僩傾僢僾偱偒側偄偲俙僶僢僋僗偐傜尵傢傟傔傫偳偔偝偔側偭偰庢傝晅偗傪巭傔偰偄偨偺偱偡丅
丂崱夞暉搰巗偺幮夛幚尡偲偟偰丄曈缈側偲偙傠偵俤俿俠偺僎乕僩傪偮偔傝丄偦偙傪棙梡偟偨応崌偼丄彆惉嬥傪弌偡丄偲偄偆惂搙偱偡丅崱夞怽偟崬傫偩偲偒丄2000戜偺曞廤梊掕偵懳偟偰丄屻100戜偱偡丄偲偄偆偲偙傠傑偱彆惉偼恑傫偱偄偨偺偱偟偨丅婡婍偑13860墌庢傝晅偗偵8000墌傎偳丅偙傟偵懳偟偰丄彆惉5000墌丄僇乕僪偺億僀儞僩6550墌傪崱夞巊梡偟偰丄嵎偟堷偒1枩1愮墌傎偳丅
丂50000墌偺慜暐偄偱58000墌偺棙梡偑偱偒傞惂搙傪巊偭偰傕丄俤俿俠偺儊儕僢僩偑弌偰偔傞偺偼丄偟偽傜偔愭丅偄傢偒傊峴偔偲曅摴3,000墌傎偳偺崅懍椏嬥丅偲偡傞偲丄栺10夞偱58000墌丄師偺58000墌偱丄傛偆傗偔儊儕僢僩偑丅俤俿俠偺婡婍戙嬥丄庢傝晅偗旓梡傪夞廂偡傞偺偵丄15枩墌埲忋僴僀僂僄僀僇乕僪乮媽乯傪攦傢側偔偰偼側傜側偄丅偙傟偼偳偆峫偊偰傕丄偍偐偟偄丅摴楬岞抍偼俤俿俠庢傝晅偗旓梡傪慡妟弌偡傋偒偩丅晛捠偺恖偼丄俤俿俠偼偮偗側偔偰傕偄偄傛側偭偰峫偊偰偟傑偆丅
丂嵟嬤偁傞曽偐傜丄偙傟傑偱偺俀俠俫偐傜丄儅儖僠丄僒儔僂儞僪偵偟偰傒偨偄偲憡択偝傟偨丅尰忬偺僔僗僥儉傪幪偰偰丄俙倁傾儞僾傪擖傟傛偆偲偄偆偺偩丅偦偆姪傔傞斕攧揦傕斕攧揦偩丅
丂尰忬偺俀俠俫偺僔僗僥儉傪婎杮偲偟偰丄儕傾俠俫傪捛壛偟偰丄4俠俫僒儔僂儞僪傪帋偟偰偄偗偽傛傠偟偄偺偱偼丄偲傾僪僶僀僗偟傑偟偨丅5.1俠俫偼晹壆偺峀偝偐傜偟偰擄偟偄丅俽倂傪抲偔応強偑側偄丅
丂塮憸傪擖傟傞応強偑側偄丄偲偄偆丅偦傟傕丄尰忬偼僽儔僂儞娗丅偦傟傪偳偆傗偭偰僒儔僂儞僪丄戝夋柺偵偟偰偄偔偐丅
丂尰忬偱偺偍姪傔偼丅
侾丏僩儔儞僗億乕僩丅傾僫儘僌弌椡晅偒丄偐偮丄僙儞僞乕儗僗丄俽倂儗僗偱丄懠僠儍儞僱儖偵偦偺壒惡傪怳傝暘偗傞婡擻傪帩偭偰偄傞傕偺丅偲偄偆偲丄倀倃亅侾偟偐側偄丄偐丠拞屆偱70枩墌戜丅
俀丏儕傾僗僺乕僇乕丅峀偝偼6忯偱偺僒儔僂儞僪嵞惗偲偡傞偲丄儕傾偼儈僯僗僺乕僇乕偐丅壒偺弌傞彮偟傑偲傕側俽俹傪儕傾偵僙僢僩偟偰丄偲偵偐偔僒儔僂儞僪壒惡傪弌偟偰傒傞丅偦傟傪嬱摦偡傞丄傾儞僾丄僾儕丄僷儚乕偺僙僷儗乕僩偑柍棟側傜丄彮偟傑偲傕側僾儕儊僀儞傾儞僾傪帩偭偰偔傞丅拞屆偱5枩墌掱搙丅
俁丏僾儘僕僃僋僞乕丅嵟嬤俢俴俹僾儘僕僃僋僞乕偼30枩墌僋儔僗偱傕椙偄傕偺偑弌偰偒偰偄傞偺偱丄嶰旽偺怴婡庬偁偨傝偱栺30枩墌丅僗僋儕乕儞偼搳幩嫍棧偑偳偺偔傜偄庢傟傞偐栤戣偩偑丄40偐傜70僀儞僠偼庢傟傞丅尰忬偺21乣29宆僋儔僗偺僥儗價傛傝偼戝夋柺偵側傞丅側偤僾儘僕僃僋僞乕偐丅戝夋柺偺塼徎偼傑偩傑偩崅偄丅僾儔僘儅傕摨條丅50丄60丄70僀儞僠偲僒僀僘偑偁偑傞偵偮傟敆椡攞憹丄姶摦傕斾椺偟偰戝偒偔側傝傑偡丅僗僋儕乕儞偼儘乕僐僗僩偺俶俙倁俬俷偱廫暘丅偙傟偱3丄4枩墌
丂僩儔儞僗億乕僩傪彍偗偽5丄60枩偱偲傝偁偊偢僒儔僂儞僪偡傞娐嫬傊帩偭偰偄偗傞丅僩儔儞僗億乕僩偼擄偟偄丅尰忬偱丄僄僜僥儕僢僋偺倁俼俢俽儊僇傪巊偭偰俀俠俫傪妝偟傫偱偄傞曽側偺偱丄偦傟偲摨摍埲忋偺俀俠俫嵞惗擻椡傪帩偭偰偄側偗傟偽丄僒儔僂儞僪丄儅儖僠俠俫偼摫擖偟偰傕偡偖朞偒偰偟傑偆偱偟傚偆丅俢俤俶俷俶偺儅儖僠僾儗乕儎乕偼丄僙儞僞乕儗僗偺愝掕偲偐偱偒傞偺偱偟傚偆偐偹丅
僷僀僆僯傾偺俢倁969俙倁i偼塮憸偼僺僇僀僠側偺偱偡偑丄壒偼偄傑偄偪丅僟僀儗僋僩偱丄傾僫儘僌弌椡傪暦偔応崌丄偐側傝偑偭偐傝偟傑偡丅塮夋偟偐尒側偄偺偱偁傟偽丄壗偲偐変枬偱偒傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄掅堟偑僷僀僆僯傾偺僪儘乕儞偲偟偨壒側偺偱丄偙傟偼僷僗丅壗偟傠倁俼俢俽傪搵嵹偟偰偄傞儐僯僶乕僒儖僾儗乕儎乕偼倀倃-1偲倀倃-3偟偐偁傝傑偣傫丅倀倃-3偼儕傾僠儍儞僱儖偺傾僫儘僌弌椡偑柍偄偺偱僒儔僂儞僪嵞惗偑扨昳偱偼偱偒傑偣傫丅倀倃-3+俙倁傾儞僾傪攦偆傛傝丄倀倃-1傪攦偭偨傎偆偑埨偔側傞偲偄偆偙偲偱偡丅
丂僩儔儞僗億乕僩偑寛傑傞傑偱偼師偺僗僥僢僾偵恑傔傑偣傫偹丅偑傫偽傟俫偝傫丅
仜丂20050531丂丂儗儞僞儖
丂俛俷俵偺嵟廔戄偟弌偟偺偲偒丄僕僷儞僌偺怴嶌倁俷俴5傪庁傝偰偒偨丅懠偼丄捠忢斉丅偙傟偑1廡娫戄偟弌偟丅偲偙傠偑怴嶌偼2攽3擔側偺偩偭偨丅捠忢斉偺曉媝偺偮傕傝偱曉偟偵峴偭偨傜丄偄偒側傝墑懾椏傪560墌傕惪媮偝傟偨丅偔偭偦乕両両戝幐攕丅
丂俢倁俢偺僶僢僋傾僢僾偺榖丅塮憸偼丄傾僯儊偼傎偲傫偳僆儕僕僫儖丅堦斒摦夋偼庒姳娒偔側傞傕偺偺丄俽倁俫俽傛傝偼椙偄丄偲偄偆儗儀儖偱僶僢僋傾僢僾偱偒傞丅偲偙傠偑丄壒惡偵偮偄偰偼丄僾傾乕偵側偭偰偟傑偆丅
丂壒惡偵偮偄偰偼丄彂偒崬傒偺懍搙偑塭嬁偡傞偲偄偆斕攧揦俲偝傫偺俲俲偝傫偺榖偑偁偭偨丅偦傟偱幚尡傪偟偰傒偨丅彂偒崬傒僜僼僩偼僱儘丅愝掕偱丄彂偒崬傒懍搙傪1攞偲偐2攞側偳抶偔偱偒側偄丅抶偔偟偰4攞丅幚嵺偵摦偐偟偰傒傞偲丄彂偒崬傒偼16攞偵側偭偨丅偟傚偆偑側偄偐傜丄偦偺嵟掅偺懍搙丄偲嵟崅懍乮偙偺2庬椶偟偐僱儘偱偼慖戰偱偒側偄乯偱丄僶僢僋傾僢僾僨傿僗僋傪嶌惉丅壒偺堘偄傪専徹偟偰傒傛偆丅尦僜乕僗偼丄挻愨僫僠儏儔儖榐壒丄戝娧柇巕偺俠俢傾僩儔僋僔僆儞丅寢壥偼屻傎偳丅
丂5寧29擔偵暉搰巗暥壔僙儞僞乕偱丄搶嫗岏惉僂僀儞僪僆乕働僗僩儔偺僐儞僒乕僩偑偁偭偨丅僠働僢僩戙傕儕乕僘僫僽儖丅柡偲擇恖偱娪徿偵峴偭偨丅搶嫗岏惉僂僀儞僪偺僨傿僗僋偼丄2002擭偺僔僇僑儔僀僽偺俽俙俠俢偑偁傞丅偙傟偼桪廏榐壒偲偄傢傟偰偄傞傕偺丅俆丏侾俠俫偩偑丄僙儞僞乕偵偼傎偲傫偳妝婍壒偼擖偭偰偍傜偢丄夛応偺僙儞僞乕壒偺傛偆偩丅儕傾傕儂乕儖埫憶壒傪娷傔儂乕儖僄僐乕偑婰榐偝傟偰偄傞丅
丂幚嵺偵惗偱暦偄偨屻丄摨偠墘栚偼丄儅僗僋偲偄偆僆乕僾僯儞僌偺嬋偩偗偩偭偨丅俙倁儖乕儉偱暦偄偰傒傞偲丄摨偠嬋偵偼暦偙偊側偐偭偨丅偦傟偧傟偑堘偆嬋偺傛偆偩偭偨丅柡傕丄偙傫側墘憈偩偭偨偐丠偲庱傪偐偟偘偨丅摿挜揑側偝傃偺儊儘僨傿偼晹暘揑偵妎偊偰偄傞偑丄懠偺晹暘偼丄暦偒妎偊偑側偄丅傾儗儞僕偑堎側傞偺偩傠偆偐丠偦傟偲傕丄僆儞儅僀僋偱榐壒偝傟偨嬋偲丄暥壔僙儞僞乕偺恀拞偁偨傝偱暦偔壒妝偼堎側傞偲偄偆偙偲偐丠
丂慜敿偑僋儔僔僢僋宯偺妝嬋丄媥宔傪偼偝傫偱丄屻敿偼僕儍僘宯偺妝嬋偩偭偨丅俙楍幵偱峴偙偆丄偼丄埨怱偟偰暦偗偨丅傗偼傝僾儘偺妝抍偼慺惏傜偟偄丅僗僀儞僌僈乕儖僘偺墘憈偲偼堦慄傪夋偟偰偄偨丅
仜丂20050524丂俛俷俵戄偟弌偟嵟廔擔
丂側傫偲傕斶偟偄偙偲偩偑俛俷俵暉搰惣岥揦偑23擔嵟廔戄弌擔偩偭偨丅旂擏偵傕僕僷儞僌倁俷俴俆偑怴擖壸偟偨擔偩偭偨丅偄偮傕偼俲俲偝傫偐傜庁傝偰偄偨偺偩偑丄嵟廔擔偲偄偆偙偲偱丄庁傝傞帠偵偟偨丅
丂懠偵丄僗僞乕僩儗僢僋俢倁俢僔儕乕僘傪庁傝偰丄俛俷俵偺嵟屻偺儗儞僞儖偼廔椆丅
丂僗僞乕僩儗僢僋傕丄榖偵傛傝丄夋幙偺偽傜偮偒偼戝偒偄丅戞侾榖偼丄僽儖乕偺怓偢傟偑偼側偼偩偟偄丅夋幙傕儃働婥枴丅
丂怴偟偄榖偵側傟偽側傞傎偳丄夋幙偼椙偔側偭偰偔傞丅俴俢偱偼偙偺夋幙偼弌偣側偄丅
丂僕僷儞僌偼丄尨嶌枱夋傪撉傫偱偄側偄偺偱丄側傫偲傕偩偑丄偳傫傁偪偑側偐側偐巒傑傜側偄丅偍偝偊偰偄傞偺偼敾傞偑丄攋夡偺僇僞僗僩儘僼傿偑彮側偄丅俽俥側偺偩偐傜峔偊偰偄側偄偱偝偭偝偲偳傫傁偪傪偼偠傔偰傎偟偄丅
仜丂20050512丂丂俛俷俵暵揦
丂儗儞僞儖垽梡揦暉搰墂惣岥偺俛俷俵揦偑崱寧偱暵揦偲側傞丅僣僞儎偵暪崌偝傟偰偟傑偆偨傔傜偟偄丅
丂儔僀僽儔儕乕偺崁偱婋湝偟偨捠傝丄揦偑側偔側傞偲儔僀僽儔儕乕偑側偔側傞丅偼偁丅
丂僣僞儎偱偳偺傛偆側昳懙偊傪偟偰偔傟傞偐晄柧丅
丂埲慜儌僨儖俋俿偺儗僢僌偵憰拝偟偰偁偭偨庽帀偺崟偄墌斦偑側傫側偺偐晄柧偲彂偄偨偑丄崱擔敾柧偟偨丅
丂俰侾俹偺惢昳偩偭偨丅俬俠俹僐儞億僕僢僩俹俙俁俆俢乛係俹偩偭偨丅朰傟傞傕傫偱偡偹偊丅
丂惵偺俬俢俽僐儞僕僢僩偲偼堎側傞俰侾俹偺惢昳丅俬俠俹傪俬俢俽偵懼偊傞偳偺傛偆偵側傞偺偩傠偆偐丠憗偔傾儞僾偑栠偭偰偒偰傎偟偄丅
丂暉搰偺俶揦偱偼揦撪柾條懼偲側傝丄俰侾俹偺惢昳偑偳乕傫偲揥帵偝傟偰偄偨丅
仜丂20050507丂丂僗僀儞僌僈乕儖僘
丂CD偱僗僀儞僌僈乕儖僘儔僀僽偑弌偰偄偨偺偱挳偄偰傒偨丅
丂幚偼塮憸偑偮偄偰偄側偄偲丄偐側傝偮傜偄傕偺偑偁傞丅偁偺彈偺巕偨偪偑墘憈偟偰偄傞偺偩丄偲偄偆塮憸偑偁傞偲丄僈儞僶儗乕両両偲墳墖偟偰偟傑偆偺偱偡偑丄壒偩偗暦偄偰偄傞偲丄偙傟偼丄寢峔岠偒傑偡丅墘憈偼壓庤丅
丂塮夋偺偨傔偵楙廗偟偰偆傑偔側偭偰偒偨恖偨偪偱偡偑丄壒偺傒偱暦偔偲偮傜偄丅僕儍働僢僩傗丄嶜巕偺幨恀傪尒側偑傜憐憸偟偰暦偔偺偑媑丅
仜丂20050501丂丂憗偔傕5寧
丂偁偭偲偄偆娫偵5寧丄偦傟傕岼偱偼僑乕儖僨儞僂僀乕僋偲偄偆楢媥帪婜偵側偭偰偄傞傛偆偩丅楢媥偩偐傜偲偄偭偰丄巇帠偑帺摦揑偵恑傓傢偗偱傕側偟丅媥傓偙偲=尭廂偲偄偆偍傗偫偺巇帠偺摿惈偑偁傞偺偱丄傕傠庤傪忋偘偰丄怱恎偲傕偵媥傒儌乕僪偵擖傟側偄帠忣偑偁傞丅
丂偝偰丄愭擔夡傟偨偍傗偫偺僨僗僋僩僢僾婡丅桭恖偺僷僜僐儞垽岲幰偐傜屘忈屄強偲峫偊傜傟傞僷乕僣傪庁梡偡傞偙偲偑偱偒偨丅KK偝傫桳擄偆偛偞偄傑偡丅
丂庁梡僷乕僣偼丄揹尮偲僴乕僪僨傿僗僋偩丅晄椙尰徾偼丄婲摦偑偆傑偔偄偐側偄丄偐偭偰偵僔儍僢僩僟僂儞偟偰偟傑偆丄傾僾儕働乕僔儑儞傪摦偐偡偲丄僔儍僢僩僟僂儞偡傞丄側偳丅
丂庁傝偰偒偨揹尮偼丄墱峴偒偑3僙儞僠傎偳偱偐偄傕偺偩偭偨偑丄僐僱僋僞晹偼嫟梡側偺偱丄尰忬偺傕偺傪奜偟偰丄庁梡揹尮傪庢傝晅偗偨丅
丂婲摦丅
丂偆傑偔偄偭偨丅揹尮偑偩傔偩偭偨偺偩丅晄椙揹尮傪僶儔偟偰傒傞偲丄揹夝僐儞僨儞僒乕偑僽儘乕偟偰偄偨丅偙傟偱偼偩傔偩偹丅
丂揹夝僐儞偺忋晹偑朿傜傫偱塼楻傟偟偰偄傞偺偑敾傞偱偟傚偆偐丠


丂350W偺斈梡昳偑2500墌傎偳偱攧偭偰偄傞丅庁梡昳傕摨條偺斈梡昳傜偟偄偺偱忳偭偰傕傜偆偙偲偵偟偨丅
丂偙偪傜偼柍棟傗傝墴偟崬傫偩庁梡揹尮晹丅CD僪儔僀僽偺屻晹偺僐僱僋僞偲偺寗娫偑傎偲傫偳柍偄丅
丂巊傢側偄僐僱僋僞乕傕懡偄丅傑偁丄摦偗偽偄偄傗丅
丂廋棟偟偨僨僗僋僩僢僾婡偼丄偙偺摉帪僴乕僪僨傿僗僋偑堦斣偱偐偐偭偨偺偱丄奺僲乕僩僷僜僐儞偺僨乕僞僶僢僋傾僢僾偺偍偍傕偲偵側偭偰偄偨丅
丂僶僢僋傾僢僾偟偰偄偨僲乕僩僷僜僐儞傕丄傑傕側偔峏怴偺帪婜偑嬤偯偄偰偄傞丅巇帠偺儊僀儞偵巊偭偰偄傞IBMTHINKPAD偑偄傛偄傛婋側偄偺偩丅偐側傝巊偄崬傫偱丄屻宲婡傕THINKPAD偵偟傛偆偐偲峫偊偰偄傞偑丄崅偄偺偱丄柪偭偰偄傞丅尰峴婡偺X40傑偨偼X41偼丄僨僗僋僩僢僾婡偱挻崅惈擻婡偑攦偊偰偟傑偆嬥妟側偺偩丅

丂偙偆偟偰傒傞偲丄僷僜僐儞傕壠揹側偺偩側偁丄偲巚偆丅儐僯僢僩帠偵側偭偰偄傞偑丄偦傟偧傟偺奐敪丄愝寁丄惢憿丄昳幙娗棟側偳偑偒偪傫偲偟偰偄側偄偲丄斶嶴偩丅僉乕儃乕僪偑偁偭偨傝丄僜僼僩偵傛偭偰巊偄曽偑堎側傞傕偺偺丄寢壥偲偟偰偺弌棃忋偑傝偺僾儕儞僩側傝丄暥復側傝丄偼偦偺惢昳偺惈擻傪昞偡偺偩丅
丂崱夞偺揹尮晹傪尒偰偄傞偲丄僨僕僞儖偺僷僜僐儞偲偄偊偳傕丄傾僫儘僌乮揹尮乯偑婎杮側偺偩側偁丄偲姶奡怺偄傕偺偑偁偭偨丅
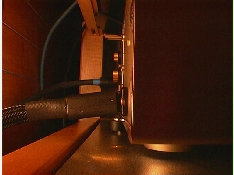 1000俹偺儕傾柺丂
1000俹偺儕傾柺丂



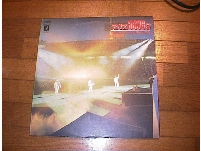
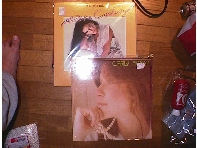
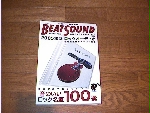



 僼儔僢僔儏偱旘傫偱傞偺偼偛垽沢丅
僼儔僢僔儏偱旘傫偱傞偺偼偛垽沢丅 丂嵞僙僢僥傿儞僌偺俵俷俢俤俴9俿丅
丂嵞僙僢僥傿儞僌偺俵俷俢俤俴9俿丅