| 方式 | 水平解像度(本) | 備考 |
| TV | 320 |
キャリアによる水平解像度の限界 ソースにLD、DVD、EDβなどをもってくるとそれなりの解像度を発揮するモニターは存在しています。 |
| VHS |
公称240 ノーマルVHS 3倍モード 180から220 標準で220から240 SVHS 350から400 |
|
| β |
水平解像度公称250。 βⅢで、180本から220。 βⅡで180から240。 βⅠで、240から270。 ハイバンドになり、βⅢで200程度、βⅡで、220から240、βⅠで240から270。 EDβで500(らしい)。 |
機種によりばらつき多数 |
| LD | 350 | |
| VHD | 240 | VHSと同程度 |
| 8ミリV |
240 HI8で400 |
MEテープで高画質録画。 |
| DV |
500 ハイビジョンで1080I(1000くらい) |
|
| DVD | 480I(480くらい) | これをアップスケールングで720P |
| WVHS | アナログでハイビジョン記録できるフォーマット。WVHSテープを使うと長時間モードで高画質記録が出来る。 | 現状ではコンポ、テープともにレガシー化。 |
| DVHS | デジタルでハイビジョンまる取り。 | |
| BSハイビジョン | 1080I | 画質は、転送レートで決まってしまう。 |
| BD、HDDVD | 1080P | 画質は転送レート、音質はビットレートに大いに関与する。 |
| SDカード、HDDなど | 1080I、1080P | ハイビジョン画質で録画可能。 |
| 方式 | 転送レート |
| CD | |
| LD | |
| 地デジ | HD 17Mbps(12から18) |
| BS |
HD 24Mbps(NHKBS) 20から18(WOWOWなど) SD 12Mbps |
| DVD | 約5.6Mbps |
| BD | 最大72Mbps(通常30Mbps程度) |
| 方式 | ドルビーデジタル | DTS | LPCM |
| CD | 1.4M | ||
| LD | 384K | ||
| 地デジ | |||
| BS | |||
| DVD | 448K | 768から1536k | |
| BD | 640K | 1.5M | 4.6M |
| HDMIバージョン | 規格策定年 | DolbyDjital/DTS | DVDオーディオ | SACD | DolbydigitalPlus,DolbyTrueHD,DTSHDHighResolutionAudio,DTSHDMasterAudio |
| 1.0 | 2002 | ○ | |||
| 1.1 | 2004 | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 2005 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2a | 2005 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.3 | 2006 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.3a | 2006 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バージョン | PCM | 映像解像度 | 色深度 | 色域規格 | フレーム/秒 |
| 1.0 | 2CH | 1080P | 8bit | sRGB | 60 |
| 1.1 |
8CH (7.1CH) |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 1.2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 1.2a | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 1.3 | ↓ | 1440P | 16bit | xvYCC | 120 |
| 1.3a | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| HDMI | バージョン | 内容 | 備考 |
| HDMI | 1.0 | 4.95Gpbs 165Mhz(1080P) | ※8bit×3=24bit 2002年策定 |
| HDMI | 1.1 | DTS音声対応等 | |
| HDMI | 1.2 | PCモニター対応 | |
| HDMI | 1.2a | 機器リンク対応 | |
| HDMI | 1.3 | 10.2Gpbs 340Mhz 16bit×3=48bitカラー |
| D規格 | 名称 | サイズ | 周波数 |
| D1 | 通常のDVD | 720×480i(525i) | 29.97HZ |
| D2 | プログレッシブDVD | 720×480P(525P) | 59.94Hz |
| D3 | ハイビジョンHD | 1920×1080i(1125i) | 29.97Hz |
| D4 | ハイビジョンHD | 1280×720P(750P) | 59.94Hz |
| D5 | プログレッシブHD | 1920×1080P(1080P) | 59.94Hz |


 プロローグ6のレッグはゴム製です。そこに3点支持でスパイクを挿入しました。
プロローグ6のレッグはゴム製です。そこに3点支持でスパイクを挿入しました。 音がどしっと来るのです。
音がどしっと来るのです。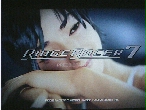 リッジレーサー7 PS3ゲームソフトのオープニングアニメ。D端子入力で1080I。DPX1000の静止画を撮影しました。ご覧のように美しいものです。現物はもっときれいです。ちゃんと女の子の頬にそばかすまで表現されています。
リッジレーサー7 PS3ゲームソフトのオープニングアニメ。D端子入力で1080I。DPX1000の静止画を撮影しました。ご覧のように美しいものです。現物はもっときれいです。ちゃんと女の子の頬にそばかすまで表現されています。 AX1600。RCA6本の接続をどうしよう。とりあえず、室温になじませる。
AX1600。RCA6本の接続をどうしよう。とりあえず、室温になじませる。 暗闇に光る真空管の妖しい光芒。
暗闇に光る真空管の妖しい光芒。 カードスロット
カードスロット 各種端子
各種端子  PlimaLuna ProLogue Six
PlimaLuna ProLogue Six 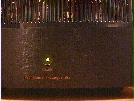



 こちらは、MODEL9Tを修理に出したあと、臨時で置いているPA70CE(右)。ブリッジ接続で鳴るようになっています。
こちらは、MODEL9Tを修理に出したあと、臨時で置いているPA70CE(右)。ブリッジ接続で鳴るようになっています。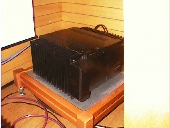 ゾウセカスに載ったPA70CE。ブリッジ接続で結構鳴る。
ゾウセカスに載ったPA70CE。ブリッジ接続で結構鳴る。

